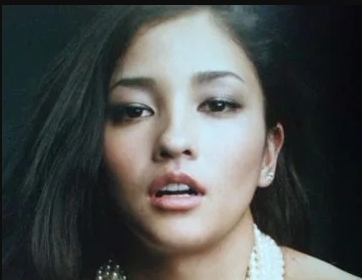
妄想小説
潜入捜査官 冴子 第二部
三十五
「ああ、駄目っ。イクっ。イッてしまいそうよ。アア、イクぅ・・・。」
鬼源の激しい指使いに合せて、冴子も大きく自分の腰を振り始める。
その時だった。突然、鬼源の指が冴子の陰唇からすぽっと抜けてしまったのだ。
(えっ?)
「ううっ・・・。」
冴子が声を挙げそうになるのと同時に鬼源の口から呻き声が洩れてきた。我に返って目の前の鬼源の様子を見ると胸を掻き毟りながら鬼源が床に倒れているのだった。明らかに心臓絡みの発作の症状だった。
(危険だわ。何とかしなくちゃ。)
「だ、誰かっ・・・。誰か居ないのっ・・・。誰か来てえーっ。」
冴子は自分の格好も忘れて咄嗟に大声で叫んでいた。冴子の悲鳴を聞きつけたらしい者たちの足音が廊下の遠く向こうから近づいて来るのが分った。
「社長ーっ。どうかしましたかーっ。」
襖の向う側で躊躇している声がする。冴子にはもう呼び入れるしかなかった。
「社長が倒れたのよ。早く来てっ。」
襖が音を立てて開けられる。
「あっ・・・。」
男達の絶句したような声は、倒れ込んでいる鬼源に向けられたものか、奈美のあられもない姿に対してなのか区別がつかなかった。
「誰かっ。救急車を呼んで。早くぅ・・・。」
数人が鬼源に駆け寄り、あるものは携帯を取り上げて救急車を呼び始めた。その後ろからぬっと現れたのは氷室恭平だった。
救急車が到着するサイレン音が聞こえ、座敷に担架が運び込まれ、男達によって鬼源社長が運び出されてしまう間、奈美はずっと股間と乳房を晒しながら柱に縛り付けられたままだった。その間、男達は奈美の存在を無視するかのような素振りはしているものの、時々ちらっ、ちらっと盗み見るような視線を感じないわけではなかった。
最後に男達が出て行った時、座敷に残ったのは恭平、ただ一人だった。
「ねえ、もういいでしょ。これを解いて頂戴。」
懇願する奈美の声に、くるりと振向いた恭平の口は歪んだ笑みを浮かべていた。
「そうはいかねえな、奈美さんよ。」
「えっ、どういう事・・・?」
「おめえさんみたいなじゃじゃ馬を懲らしめるには又と無いいい機会だからな。」
「わ、わたしが手出し出来ないのをいいことに、悪戯でもしようという気なの?」
「悪戯だって? あの様子じゃ、未遂に終わったようだな。オジキに代わってアンタを天国へ送ってやろうっていうのさ。」
「何考えているの。ここは鬼源社長の座敷よ。ここで私に狼藉を働こうって言うの? そんな事したらどういう事になるか、貴方わかっているの?」
「大丈夫さ。ここにはおめえと俺しか居ないんだ。おめえが口を噤んでる限りオジキにはばれやしねえよ。」
「わたしが社長に言わないとでも思っているの?」
「俺とやってみりゃわかるぜ。あんな老いぼれたオジキのチンポなんかよりいいに決まってるだろ。一発やりゃ、俺の虜になるに決まってるだろ。」
「随分と自惚れているのね。じゃ、試してみたら。」
「へっへっへっ。おめえもやりたくてたまらないようだな。おっと・・・。そんな位置じゃ幾ら俺のチンポが上を向いてたって奥まで挿し込むのは難しいな。まだ縄を解いてやる訳にはゆかんが、柱からは外してやろう。」
そう言うと、恭平は奈美を柱に括り付けている縄だけを解き始める。

次へ 第二部 先頭へ