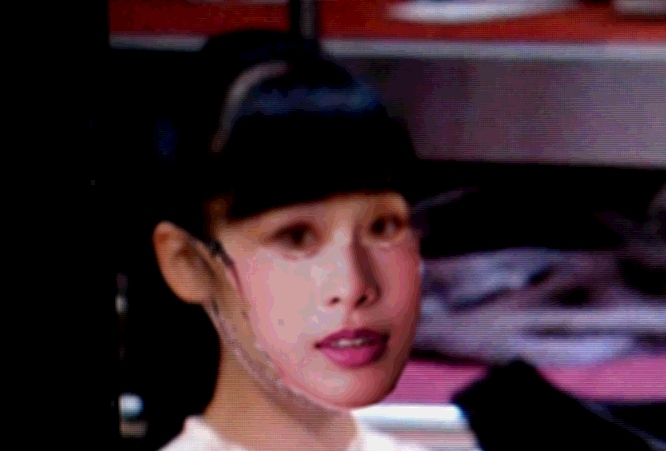
妄想小説
ワンピースの女
九
結びの一番が終わって貴子も漸く立上ろうとしたのだが、漏れ出す筈はないと思っていながらも冷や冷やしながらそっとゆっくり立上った貴子だった。紙オムツの吸収体は既に溜まった水分を吸い取って固めてくれているのだが、股間を縦に割っている荒縄と帯に浸みこんだ分だけはさすがに吸収体ではどうにもならない部分で、貴子自身もそのじわっとした湿り気の嫌な感じを気づかないわけにはゆかないのだった。気になるのは臭いが洩れだしてはいないかで、自分では微かにアンモニア臭がするような気がするだけに、まわりの視線が気になって仕方なかった。紙オムツも外したいが、それでは濡れた縄と帯が剥き出しになってしまうのでそれも出来ない。帰りの車の中でまた尿意を催さないとも限らないこともそれを躊躇させる一因ではあった。
「キヨ。今日はお前は電車で帰って。わたし、独りで帰りたいの。」
迎えに来た車からキヨの姿が見えるなり、貴子は毅然としてそう言い放った。キヨが来る時の車を降りる際に袱紗に入れて渡したものを事前に観ていない筈はないと貴子も分かっていた。いや、それだけにそれを知っているキヨと並んで車の後部座席に座りたくなかったのだ。
「そうですか。よろしゅうございますけど。では、お独りで。」
そう言って車を降りたキヨを送ると、貴子は運転手に前席と後部座席を仕切ることが出来る分厚いガラス扉を閉めるように命じたのだった。源蔵のものであるそのリムジンは、源蔵が同乗者と聞かれてはならない話をする際に分厚いガラス扉で仕切りをすることが出来るようになっているのだった。運転席に臭いが洩れないようになったのを確かめると、貴子は後部座席横の窓を少し開いて、外と空気を入れ換えながら素知らぬ振りをしていたのだった。
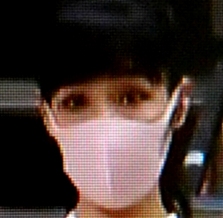
次へ 先頭へ