
妄想小説
ワンピースの女
七
(あと、もう一番だわ。)
結びの一番の呼び上げが始まって貴子は出てもいない額の汗を拭うような仕草をする。尿意は確かに忍び寄ってきていた。しかし家に戻るまで何とか我慢し通せるだろうとふんでいた。正座の方は子供の時から茶道とお華のお稽古で慣れているのであともう数時間あろうとも平気だった。しかしさすがにそれだけ長い時間尿意を耐えるのは辛かった。それは普段は感じたことのない股間への締め付けのせいもあるようだった。
源蔵が言っていた(裸でまわしを締めている力士たちの気持ち)というのが貴子にも嫌というほど味わわされたと言ってよかった。ワンピースに隠れて誰にも知られていないとは思うものの、目の前をまわし姿の力士が通り過ぎる度に、否が応でもスカートの下の荒縄と襦袢の帯の締め付けが、言い様のない違和感をもって貴子を苛み続けたのだった。
「只今戻りました。お爺様」
恭しく貴子が帰宅を告げに源蔵の前へ向かったのは、挨拶することが目的ではなかった。
「ほう、戻って来たか。どうであった。力士の裸姿は。」
「・・・。お相撲さんの大変さがわかったような気がしました。」
貴子は問われるであろう質問に帰りの車の中でずっと考えていた答えを口にした。
「どうだ。親近感が持てたか?」
「あの・・・。もう、外して頂けないでしょうか。帰り道からずっと我慢をしているのです。」
「我慢? 何をだ。」
貴子には老人が判っていて訊いているのだと重々承知していた。悔しさを堪えながらやっとのことで言葉を口にする。
「あの・・・、おトイレに行きたいのです。」
「ほう? そのままじゃ出せないのか。」
「む、無理です。どうか、お赦しください。」
半分涙目になりながら貴子は訴える。
「仕方ないな。そこの床の間に置いてある日本刀を取りなさい。」
貴子は以前に古物商が持ってきた骨董品の日本刀を取りに行く。任侠ものの映画に出てくるような鍔の無い仕込み刀で、無許可で持って居れば銃刀法違反になるのを知っていて古物商が所有者責任とばかりに高額で置いて行ったものだ。
「スカートを捲って尻を出しなさい。」
貴子は言われた通りにする他なかった。背中の結び目に老人の指が捻じ込まれるのを感じたと思ったら、すうっと腹を抑え込んでいた力が抜けた。老人の手に握られたままの、切り取られた縄と帯を取り返したかったが貴子にはもうそんな時間のゆとりはなかった。股間を抑えるようにしながら擦り足で廊下を抜けてトイレに向かうのがやっとだったのだ。
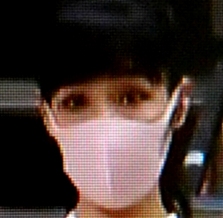
次へ 先頭へ