
妄想小説
ワンピースの女
三十六
「ふふふ。おもらしか。いい格好だな。お嬢さんらしくもないぜ。」
男の非情な言葉に貴子は顔も挙げられず、太腿から洩れだした雫がせめて便器の中に落ちるようにと脚をすぼめる。しかし半分は床のタイルを虚しく濡らして流れ出てしまうのだった。
「もう充分出たか。どうだ。自分が濡らしたまわしを締めている気分は?」
あまりの事に貴子はその場にしゃがみ込んでしまいそうになる。じっとり濡れた帯が股間にまとわりつくようで気持ちが悪くて仕方がない。
「それじゃあ着替えを持ってきてやるからここで待って居ろ。内側から鍵を掛けても構わんぞ。そんな格好で居るところを誰にも見られたくないだろうからな。但し、俺の声が聞こえたらちゃんと鍵を開けるんだぞ。さもないと一晩中その格好で過ごして最後はビルの警備員に捕まることになるんだからな。じゃ、そこで待ってろ。」
男はそう言うと惨めな格好の貴子を一人残してドアの向こうに姿を消したのだった。
男に言われた通りに内側から多目的トイレの内鍵を掛け、泣きながら待っていた貴子の元に男が戻ってきたのはそれから30分は時間が経っていた。男の声に後ろ手で内鍵を外して男を中へ招き入れた貴子は、力なく男に背を向けてぐっしょり濡れた帯を男が解いてくれるのを待った。手錠を掛けられた背中の両手が邪魔にならないように上に持ち上げて裸の尻を露わにしなければならないのは貴子にとってこの上ない屈辱だった。
きつく締め上げられた帯がやっと緩んで貴子はやっと濡れそぼった気持ちのわるいおしめのような帯から解放された。男から股間を拭って貰えるとは思っていなかったが、男が持ってきたのは着替えの下着ではなく、紙オムツなのだった。
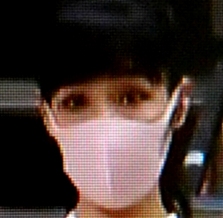
次へ 先頭へ