
妄想小説
ワンピースの女
八
千秋楽まではまだ何日もあった。こんな事が続けばいつか粗相をしてしまう羽目になりかねないと貴子は不安で仕方なかった。しかし貴子を青褪めさせたのは、この日も同じように婆やのキヨに相撲に出る前の儀式として下半身に荒縄と帯を締め込まされて源蔵の前に挨拶に出た時の事だった。貴子の目の前の珈琲テーブルの上にはグラスに並々と注がれたビールが置いてあったのだ。
その日は午前中から極力水分を採らないように気を付けていた貴子だったが、その微かな願いをも打ち砕くかのような源蔵の企みに貴子は血の気が引く思いだった。
「相撲観戦は喉が渇くだろう。それを呑んでからゆきなさい。お前はビールはいける口だった筈だな。」
「は、はい・・・。」
源蔵の企みを知っていて断われる筈も無かった。貴子は自分の運命を呪いたい気持ちだった。
「さ、遠慮せずにそれを呑み干すのだ。テレビでお前が中継で映るのを愉しみにしているよ。」
貴子は東の花道の下で正座して尿意に堪えている自分を眺めて悦にいっている目の前の源蔵の姿を想像していた。震える手でグラスを掴むと、毒でも呷るように一気にそれを呑み干すのだった。
「送りの車を降りる際に同乗してゆくキヨに『アレをお願いします』と言うのだ。わかったな。」
老人は謎の言葉を残すと貴子を送り出したのだった。
「キヨさん。あのアレ・・・。アレをお願いします。」
車が国技館の前に着いて降りる際にそのまま車に乗って屋敷に戻るキヨに謎の言葉を口にしてみた。
「ああ、旦那様から預かっておりますよ。はい、これっ。」
キヨは袱紗に包まれたものを懐中から取り出すと貴子に差し出すのだった。
狐につままれた面持ちでそれを受け取って国技館の玄関へ向かう貴子は場内に入る前にふと思い立って袱紗をそっと開いてみる。始めは何だか判らなかったのが、半分以上開いてみて、大人用の紙オムツであることをやっと悟ったのだった。
何度も躊躇ったが、中入りの始まっている会場に入る前に貴子は袱紗を手に女子トイレへ向かう。褌として嵌められた縄と帯の下にそれを着用するのは土台無理なことと判っていた。それでもそれを着用しない訳にはゆかないのだった。独り個室の中でごわごわするそのモノを帯と縄の上から嵌めて横のギャザーを留める。大人用でもLサイズらしく、まわしとしての縄と帯の上からそれを着けてもなんとか横のテープは留めることが出来、貴子はほっと胸を撫で下ろす。
その時はとうとう三役揃い踏みの頃やってきてしまった。尿意は席に着いた時から既にあったのだが、さすがに座ったままするのはどうしても躊躇われ、先延ばしにしている間に三役揃い踏みまで来てしまったのだ。
制限時間一杯になる前の四股踏みから取り組みの最中まではカメラは向こう正面をずっと捉えている。勝敗が付いて取り組み場面の再生になると花道付近にカメラが切り替わるので貴子の姿がテレビ画面に大写しになってしまう筈だった。出来ればその時を避けたかった。しかし、そのつもりでいて、これから三役揃い踏みとなる際に三役が入場するので最後の大関が準備が終わるまでずっとカメラが花道側を映したままであることを忘れていたのだった。準備が終り大関が土俵に上がってしまえばカメラは中央に切り替わる筈だった。しかしその時まで貴子は待ちきれずに限界を迎えてしまったのだった。
マスクをしたままなので表情には出なかったかもしれないと思ったが、自信はなかった。身体はきちんと正座したままだったが、その足を揃えて座る中心に生温かいものが溢れてきた時、どうにも堪らずに腰を浮かしかけてしまったのに気づいていた。周りで自分の様子に気づいて自分の方に注目している者は居る筈はないと思っていても誰かに覗かれている気がしてならなかった。少なくともテレビカメラの向こう側でその瞬間を今かいまかと注目している、こんな事を仕掛けた本人独りを除いてはなのだが。
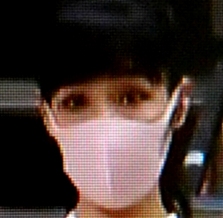
次へ 先頭へ