
妄想小説
ワンピースの女
十七
その日も貴子は一見、桟敷席で相撲を愉しんでいるかの様子を装って時折拍手などもしていたが、その視線は取り組みを終えた力士たちには向かっておらず、館内にある時計の針が結びの一番が終わる時刻に近づくことばかりを気にしていた。それと気づいているのはその姿をテレビ画面で注視しているベッド上の源蔵の他には居ない様子だった。
結びの一番が終るや、貴子は席を立ち国技館の外へ出る出口へと急ぐのだった。ただ口の中に咥えさせられたものを早く出して欲しいことばかりを考えていて、トイレに寄ることも忘れて迎えの車を捜して外に出たのだった。その貴子が見慣れた白い大型のリムジン車を車寄せの中に見つけ、近寄って行って中にキヨの姿を見つけ、ほっと安堵の息を吐こうとしたその瞬間に、思いもしなかったキヨの非情の言葉を耳にしたのだった。
「旦那様からのお言い付けで、キヨはこのままこの車で寄らねばならぬところがあります。お嬢様は今日は電車にて帰るようにとのことです。ここにスイカという自動改札用の電子カードがありますので、これをお使いになってください。」
貴子は耳を疑った。電車など女学生の時からもうずっと乗ったことが無かった。
(困ります。一緒に車に乗せてください。電車などで帰るのは嫌です。)
大声でそう訴えたい貴子だったが、マスクの下で咥えさせられているものがそれを赦さない。何台も迎えの車が順番待ちをしている中で、言葉にならない呻き声を挙げるという訳にも行かないのだった。
貴子が載せて欲しいという懇願の顔をどれだけしてもキヨにはその表情は届いていなかった。嫌、薄々は気づいていたのかもしれないが、源蔵に厳しく言われているらしく、冷たい素振りのまま迎えのリムジンのドアは閉められてしまったのだった。
車が走り出し、独り残された貴子は途方に暮れていた。自分が降りるべき最寄りの駅名だけはかろうじて判るが、何処からどの線に乗ればいいのかも判らなかった。取り敢えず電車で帰るらしい人々が歩いていく方向へ自分も倣って歩いて行く。貴子は階段を降りることで地下鉄に向かっているらしいことだけは判った。
改札の近くで自動券売機の上に路線図があって、そこに自分が降りるべき駅名を見つけてやっと安堵の息を吐いたのだった。
スイカという電子カードも前の人の様子を観て何とか理解し通過出来たが初めての経験でどきどきしながらの事だった。
漸く自宅へ帰る方向の電車に乗り込み、電車のドアが閉まった時にトイレに寄っておくべきだったことに気付いた。以前のように何かを仕込まれたビールを出掛けに呑まされた訳ではなかったので相撲観戦中に催すまでの事はなかったが、さすがに家を出てからかれこれ5時間近くが経過していた。家までの時間が判らないだけに辿り着くまで我慢出来るか自信がなかった。
乗り込んだ駅から二つ目まで来た際に、乗り込んだ時にはさほどではなかった車内がどんどん混み始めていた。貴子は普段、電車に乗る事はおろか外出も滅多にしないので混み合う時間帯という意識がなかったが、明らかにその時間帯は夕刻の帰宅ラッシュ時に差し掛かっているのだった。車内が混んでくるに従って貴子はどんどん車内奥へ押し込まれていく。ドアとドアのちょうど中間まで来ると、そこから先は駅に着くたびに増えてくる乗客たちに揉まれて身動きも出来なくなってしまう。
貴子が身体に異変を感じたのはぎゅうぎゅう詰めで身動き出来なくなってからすぐの事だった。背後に、というより明らかにお尻の辺りに妙な感覚を憶えたのだ。それは貴子に女学生だった頃のある記憶を蘇らせていた。
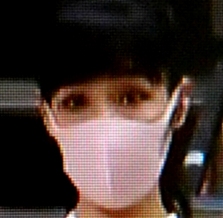
次へ 先頭へ