
妄想小説
ワンピースの女
十九
「で、君はいつそれに気づいたのかね?」
「バスに乗り込んで割とすぐだったと思います。」
生徒指導の教官としては最年長の有住が、貴子は苦手だった。そのねちっこい爬虫類のような眼でじろっと睨まれると、身が竦んでしまう思いがするからだった。
「どんな風に感じたのだね?」
貴子は有住からの質問に、思わずさっき穿き替えたばかりの制服のプリーツスカートを見下ろす。汚されたそれは家庭科担当教師の福山が、薬品で洗い落し、アイロンで乾かした上で届けてくれたのだった。朝からずっと代わりに穿いていた体育用のジャージで生徒指導教官と会うのはどうしても嫌だったからだ。
生徒指導室は理科実験室や家庭科調理室など普段あまり使われない特殊教室が並ぶ棟の一番奥なので、ひと気がなく静まり返っていた。それでなくても狭い部屋に男性教師一人とだけ居ることに貴子は気づまりを憶えていた。
「どんなって・・・、最初は何か硬い物を押し当てられているのだと思いました。」
「最初は・・・? ということは途中から何なのかに気付いたということだよね。」
「え? ええ・・・、そうです。」
「男性の・・・だと?」
「は、はい・・・。」
「男性のあそこが、硬くなる・・・というのは知っていたのだね。」
「え? 多分・・・、そうじゃないかと。」
「君は硬くなったあそこを観た事があるのだね。」
「え、そ、それは・・・。」
貴子はすぐに養父の源蔵と一緒の風呂に入れさせられた時の事を思い出していた。初めてあそこを源蔵に剃られた時だった。源蔵は(女の子はこんなところに毛を生やしていてはいけない。それはとても恥ずかしいことなのだよ。)そう諭して自ら剃刀を執ったのだった。その時に男のモノが鎌首を擡げるのを初めて目にしたのだ。それが何を意味するのかも知らなかった頃に。
「男性があそこをそんな風にしたら、どんな気持ちでいるのか知っていたのだね。」
「い、いえっ。わ、わかりません。」
「ほう、わからないのか。で、君はどうだ。君のほうは、どんな気持ちがしたのかね、その時に?」
「え・・・? 気持ちが悪かったです。」
「どうしてだね?」
「だ、だって・・・。」
「何を押し当てられているのか、想像したからじゃないのかい?」
「想像? い、いえっ。」
「想像は・・・、してないっと。ふうん。でも気持ち悪かったのか。その何だか判らないモノが。」
「はいっ・・・。」
「逃げようとは?」
「え・・・? こ、怖くて・・・、怖くて動けませんでした。」
「ほう? どうして怖いと思ったのかね?」
「わ、わかりません。拒むようなことをすると、何をされるか判らないと思ったのです。」
「何をされる? 例えば、どんな事を?」
「わかりません。あの・・・、これ、本当に必要な事ですか?」
生徒指導の有住は質問をし返されて、見るからに不快そうな表情で眉をしかめる。
「ウチの女子生徒にこれ以上のことが起きないようにと、いろいろ考えて状況を確かめておるのだ。何だね、その言い方は。」
「す、済みません・・・でした。」
貴子は途中からこの若い生徒指導の教官が明らかに興味本位で質問をしていると気づいていた。それどころか机の下で教官自身のズボンの一部が膨らみかけているのにも気づいていたのだ。
「もういい。だいたい状況は判ったからもう行きたまえ。」
「は、はい。失礼します。」
立上って退出しようとする貴子の肩に教官は後ろから手を掛けた。
「君にも隙があったのかもしれない。以後、気をつけたまえ。」
貴子は肩に掛けられた手を振り払うかのように生徒指導室を出たのだった。
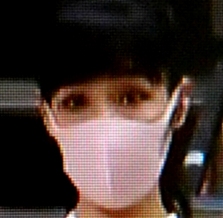
次へ 先頭へ