
妄想小説
ワンピースの女
十一
相撲観戦中に紙オムツの中に、自分自身にまわしとして締められた荒縄と正絹の帯の褌をさせられたまま、正座で放尿することを強いられるのが数日続いたのち、さすがにその仕置きにも飽きてきたようで、貴子はやっとその罰を赦されたのだった。しかし許されたのは相撲観戦に出る前に強制的に呑まされる一杯のビール(それもおそらくは中に強力な利尿剤をしこまれていたのだろう)と紙オムツを穿かされること、まわしとしての荒縄だけで、相変わらず女学生のような明るい色のワンピースの下に穿くことを赦されたのは下着ではなく真っ赤な帯の褌のみだった。
「なあ、貴子。お前がテレビに映ってしまっている姿がアップになった時のお前の顔をよく観てみるがよい。」
「マスクをしているので眼でしか顔は判りませんが、私ということがあのマスクをしていても判るのでしょうか?」
「それと思ってみていればな。しかし案外知り合いでも気づいていない者も多いかもしれぬ。儂が気にしているのはお前の顔の大半を隠しているあのマスクだ。」
「マスクがどうしたというのです? 感染予防の為にマスク着用が義務付けられているので、あの館内は相撲関係者以外はほぼ全員がマスクをしております。」
「他の者はどうだってよい。お前自身の事だ。お前が連日、観戦に来ていることを気づいている者も多いだろう。そういう連中はあのマスクの下にどんな顔が潜んでいるのかと興味深々で観ているだろうな。」
「そうでしょうか?」
「そうに決まっておる。それでふと、あることを思いついたのだ。」
貴子の胸中にまた嫌な予感が走る。
「明日の観戦にはその思いつきを実行しようと思うので愉しみにしておるのだぞ。」
「・・・。」
貴子は返事が出来なかった。
「そのテーブルの上の箱を開けてみるがよい。」
貴子が相撲観戦に出る前に源蔵に挨拶にあがった際に、老人はベッドの前に置かれているテーブルの上の木箱を指示した。
「何でしょうか。」
「開けて出してみるのだ。」
おそるおそる貴子は木箱の蓋を取って中に入っていたものを指で取り上げる。それは形容もし難い奇妙な器具のようなものだった。その器具のようなものの一部の形が貴子にあるモノを連想させた。老人は敏感にその貴子の表情の変化に気付いたようだった。
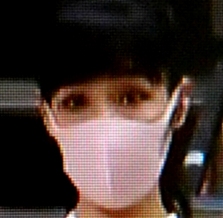
次へ 先頭へ