
妄想小説
ワンピースの女
二十二
(やめてっ。お願い・・・。帯を解かないで。)
その時、電車にブレーキが掛かったようで乗客たちは一斉に前方向に身体を振られた。
(駅だわ。逃げなくっちゃ。)
貴子は意を決して肘を曲げて大きく後ろに振り回した。誰かの二の腕にガツンと触れたようだった。その瞬間に帯を引く手が緩んだようだった。貴子は周りの人達を押しのけるようにしてドアの方へ急ぐ。
(降ります。どいて下さいっ。) そう口に出して言えない自分がもどかしかった。それでも貴子の必死のもがきを察してくれたのか、混み合った乗客たちは少し場所を空けてくれた。
「ドアが開きま~す。ご注意くださ~い。」
車内アナウンスが駅への到着を告げていた。貴子は後ろを振り返ることもせずひたすら階段へ向かうホームの上を走り続けたのだった。
改札を電子カードで擦り抜ける際に、貴子は自分のワンピースの裾から赤い帯の端が垂れ下がっているのに気づいた。帯は蝶結びの部分はすっかり解き離れて、緩く尻の上で留まっているに過ぎないのだった。しかしだからと言ってスカートを捲り上げて帯を締め直す訳にも行かず、ただ気づかない振りをして、他の誰からも気づかれないことを祈りながら走るしかなかった。
タクシーを使うことを考えて、電車用の電子カード以外にはお金に代わるものを何一つ持たされていないことを思い出して諦めたのだった。屋敷まで何とか辿り着いて、そちらで払って貰うこともタクシーなどに乗り慣れていない貴子には思いつかない話だった。
家まで歩いて帰れない距離ではないと思ったのもわざわいしたかもしれなかった。歩ける距離ではあるのだが、貴子の帰る屋敷のある方向はひと気の少ない場所を通り抜けねばならない事までも思いついていなかったのだ。
歩き出してすぐに貴子は後ろをヒタヒタとつけて来る者がいる事に気付いた。試しに足を速めてみると足音も速くなり、わざとゆっくり歩いてみると足音もゆっくりになる。しかし確実に距離は詰めつつあるのが判った。貴子はもっと早く、人家もあるうちに引返すべきだったと後悔したが、すでに人家は途絶え、道行く人も居なくなってしまっていた。
人影もない公園の脇を通り抜けるところで貴子は意を決して一気に走り出した。公園を過ぎて坂を駆け登れば屋敷はもうすぐの筈だった。しかし公園を半分も過ぎない辺りで貴子は後ろから腕を掴まれてしまった。
「あぐぅ・・・。」
声にならない呻き声が洩れる。その声に驚いたのか、貴子の腕を掴んだ手にぐっと力が篭められ、いきなり貴子は腕を捩じられた。
「うぐうぐうぐっ・・・。」
悲鳴も挙げれない貴子に為す術はなかった。捩じられた腕を持ち上げられると、その場に膝を突いて倒れそうになる。何かが貴子の足に引っ掛かったと思ったが、それは男が貴子のワンピースの裾から垂れ下がっている赤い帯の端を捉えて引っ張り上げたからだった。
(ああ、帯が・・・。)
そう思った時には帯は貴子の腰からするりとすべて落ちていた。
「ふふふ。ちょうどいいものがあるじゃないか。こいつで縛ってやる。」
(縛られる・・・?)
そう思った時には既に腰から抜き取られたばかりの帯が捩じ上げられた貴子の手首に巻きつかれていた。両手が背中で後ろ手に縛られてしまうのはあっと言う間だった。貴子は縛られたまま帯で引き摺られて公園の奥へと連れ込まれてしまう。外の通りからは灌木の茂みで見通せない場所まで引っ張り込まれると、男は貴子を縛った帯の端を手近な樹の幹に括り付けてしまう。
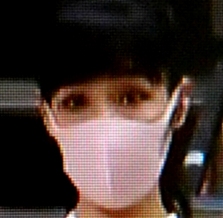
次へ 先頭へ