
妄想小説
ワンピースの女
二十九
貴子は自分の手首に掛けられたんが手錠であると判った瞬間に、脳裏をトラウマのようにしている嫌な記憶がフラッシュバックのように閃くのを感じた。
貴子が初めて自分の手に手錠を掛けられたのは、バスで痴漢にあったのと同じ女学校に通っていた時だった。それは今思い出してみても随分と理不尽ないいがかりだった。貴子の女学校に隣接する別の私立高校がすぐ近くにあって、そこは不良学生が通うことで有名な学校だった。なかでもスケ番と呼ばれる不良女子高生たちのグループに貴子は目を付けられたのだった。その頃から家のリムジンで送り迎えされている貴子の立ち振る舞いは、上品で優雅だと近隣の高校生の間でも有名だった。その事が不良女子等の癇に障ったのだ。
その日に限ってリムジンの迎えが遅れ、貴子は女学校の裏側の通用門の端で車を待っていたところに不良女子達三人が現れ取り囲まれたのだった。
「あんた、ちょっと顔、貸して貰うわよ。」
そう言って二人掛かりで強引に両手を掴まれ、学校の裏手にある丘になった小山の更に裏側にあるひと気の少ない公園に引っ張り込まれたのだった。学校とは小山を隔てているせいで、校庭の生徒たちの声も届かない代わりに、公園からの叫び声も学校には届かないのだった。
「何をなさるのですか。手を離してくださいっ。」
そう叫ぶ貴子を無視して、女達のリーダーらしき女が顎で残りの二人に指示を出すと、何時の間にか取り出した手錠を貴子の手首に掛けたのだった。
「そこの木枠に後ろ手に繋いでしまうのよ。」
「や、やめて。何、なさるの。」
「ふん、いいからおとなしくしな。ほれ、これでいい。」
女達が使ったのは勿論本物ではない玩具の手錠なのだが、鍵の造りがちょっとちゃちなだけで、貴子のような力のない女子高生の自由を奪うには充分な機能を持っていた。
「お願い。こんなもの、外してください。」
「ふん、駄目だね。お前は調子に乗ってるようだから、ちょっと反省して貰わなくちゃね。」
「わたしが何を反省しなければならないというのです?」
「お高くとまってるその態度だよ。上品ぶりやがって。お前だって、アタイ等と同じ下品なところがちゃんとあるって皆んなに知らしめてやるんだよ。」
「わたし、上品ぶってなんかいません。」
「さ、いいから。あれを呑ましちゃいな。」
「あいよ。」
女達は予め用意してあったらしいペットボトルを取り出すと、両手の自由を奪われた貴子の鼻を摘んで息が苦しくなって口を開いたところへペットボトルの口を突っ込んだのだった。
「あっぷ、うぷっ、うぐっ。」
無理やり注ぎ込まれるペットボトルの中身に貴子は咽せかえる。
「うぷっ、や、やめてっ。くるしいわ。」
「いいから、それを全部呑むんだよ。全部呑み終えたら赦してやるよ。」
「そ、そんな・・・。わ、わかりました。呑みます。呑みますから・・・。」
貴子は仕方なくペットボトルの中身を最後まで呑み干させられたのだった。
「の、呑んだわよ。これで御満足? さ、早くこれを外してっ。」
「ふふふ。駄目よ。まだね。」
「え? 飲んだら赦してくれるって言ったじゃないの。」
「これ以上呑ませるのは赦してやるっていったの。誰が手錠を外してやるって言った?」
「そ、そんな・・・。」
リーダー格の女が再び顎で合図すると、今度は用意してあったらしい段ボールの札を貴子の胸元に首から掛けると外れないように紐を引き絞ってしまう。
「何するの?」
段ボールの札には非情な文字がマジックで何やら書かれているのだった。
「こいつに目隠しを着けて見えなくするのよ。鍵はその胸の札に貼り付けておけばいいわ。」
貴子は女達にビロードの帯のようなもので目隠しを着けさせられてしまう。
「さ、誰かが助けに来てくれることを祈ることね。ま、誰かがアンタの事をみつけて、助けてやりたいって思うかどうかは判らないけどね。」
「い、いやよ。そんな事、やめて。お願い。これを解いて。」
しかし女達は準備が整ったとばかりに、自由を奪われた貴子を独り残して立ち去って行ってしまったのだった。
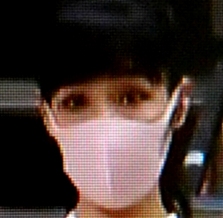
次へ 先頭へ