
妄想小説
ワンピースの女
十六
源蔵の手でいきなり突っ込まれたそれは、貴子の喉を抉るようにも思われた。口の中にすっぽり入る部分は男性のペニスそのものだが、唇部分で外から見えるそれは、赤ちゃんが咥えるおしゃぶりそのもののような格好だ。前日のモノとは違い、その唇に当たる部分の両側には髪の毛ほどの細い糸が付けられていて、それが貴子のうなじの辺りで結び合される。
「勝手に外してはならんぞ、帰って来る時まで。もしこの糸が切れていれば、きつい折檻の罰を与えるのだからな。」
「うっ、うぐうぐ・・・。」
声では返事が出来ないので、貴子は瞬きと首を小さく振ることで了解の意を示すのだった。
口に戒めが与えられている分、股間の戒めは荒縄は使われず、前日と同じ赤い襦袢用の帯がキヨの手で締められるだけで済んだ。少なくとも貴子は済んだのだと思っていた。白いワンピースの下にその赤いまわしの様な褌を着けさせられた格好で、貴子はその日も国技館へ向かう車に乗せられたのだった。
「お嬢様、それでは結びの一番が終わった頃、また迎えに参りますので。」
返事の出来ない貴子はそう告げるキヨに、(宜しくお願いします)とでも言うかのように軽く頭を下げたのだった。
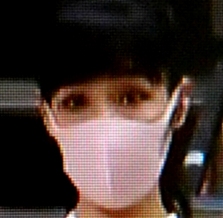
次へ 先頭へ