
妄想小説
ワンピースの女
二十六
「ではどうしてもまた往かねばならないのですね。」
「そうだ。今日は千秋楽だからな。これが最後の務めだ。」
「あれも着けてですか。」
「もちろんだ。儂はマスクの下のあれが特に気に入っておる。勿論あのドレスの下のもな。」
「だって、誰にも知られることはないではありませんか。」
「私が知っている。私だけが知っていることがいいのだ。そしてそれを着けさせられているお前の表情を観ることが何よりも愉しみなのじゃ。」
貴子は口惜しさを胸の中に噛み殺しながら言う。
「わかりました。仰るとおりに致します。ただ帰りの車の迎えだけは必ず寄こしてください。電車で帰らされるのはどうしても嫌なのです。」
「ふうん? そうか。よかろう。迎えの車はちゃんと寄こすようにしよう。」
「お願いいたします。」
そう答えた貴子だったが、ふと昨日車の都合がつかず電車で帰らせたのは源蔵がわざとそうさせた企みだったのではないかという考えが頭の中に閃いたのだった。
「では、表彰式が終わる頃迎えに参りますので、お嬢様。」
貴子は口の中に咥えさせられているもののせいで返事が出来ないので、マスクを装着した顔を軽く下げて(わかった)という表情をキヨに示した。
(あと一日、これを我慢すればいいのだ。)
そうした思いが、何とか辛い仕置きをもう一日我慢して遣りおおせようという気にさせるのだった。
この場所の取り組みはもつれにもつれこんで、千秋楽の最後の一番で番狂わせがあり、賜杯の行方は優勝決定戦まで持ち越された。しかし貴子にとっては優勝の行方がどちらに行こうが興味は全くなく、早くすべてが無事終わって呉れることだけを願っていた。
あと一番で全てから解放されるという希望を持ってじっと待ち堪えている貴子に思いもかけない事態が発生したのは、優勝決定戦に備えて最後の一線を戦う力士たちが髷を結い直す為に支度部屋へ一旦引っ込んでいる間の、館内が優勝の行方を占ってざわついている中での事だった。
東の花道際の最前列の桟敷席にひとりだけで佇んでいる貴子の桝へ一人の男が割り込んできたのだ。サングラスを掛けているのだが、横目でちらっと見ただけで昨夜の暴漢であると貴子はすぐに気付いて凍りつく。
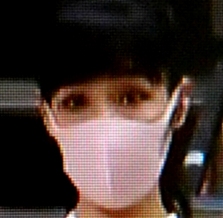
次へ 先頭へ