
妄想小説
ワンピースの女
十三
「あ、あれを・・・、あれをマスクの下で口に咥えておけと仰るのですか?」
老人がニヤリと相好を崩す。
「知らぬものはまさかそんなモノがマスクの下に隠されているとは思うまい。知っているのは儂とそれを嵌めさせられているお前だけという訳だ。どうだ、面白い趣向だろうが。」
(あ、悪魔・・・。)
一瞬、そう貴子は口にしそうになったがその言葉をぐっと呑みこんだ。貴子は泣き喚いて頼んでみたところで、源蔵がすると決めたことを撤回してくれることなどありはしないのだと嫌と言うほど知らされてきた。どんな苦痛を強いられようが、貴子にはその責め苦を堪えるしかないのだった。
「お嬢様。車が参りました。」
キヨが背後から声を掛ける。その声に返事が出来ない貴子はマスクの顔をゆっくり振って頷くことしか出来ないのだった。源蔵が目の前で口に入れて行くように命じたからだ。
最初は顎が外れそうに思えるほど苦しかった。しかし上からマスクを掛けると少し気分は落ち着いてきた。少し大き目のマスクは、口を大きく開けてマウスピースを咥えていることもすっかり隠してしまうようだった。
油断すると口の中に唾が溜まってきて、涎となって口の端から流れ出そうになる。そうなってしまう前に必死でそれを嚥下するしかないのだった。マウスピースは細いが頑丈なチェーンで首の後ろを廻して本体に錠前で繋がれてしまうので、嵌められてしまうと自分では外せない構造になっているのだった。その口枷とも言えるチェーンを貴子の長い髪を束ねたポニーテイルが上手くカムフラージュしてくれるのだ。
普段は国技館に着いて車を降りる際に初めてマスクをするのだが、その日は御付のキヨと車に乗る時からマスクをしている。キヨもその事に気づいている筈だが知らぬ振りをしているのか何も言わない。それが帰って貴子には辛かった。
「では行ってらっしゃいませ。」
国技館で車から降りる際にも貴子は返事が出来ない。何か言おうとすれば呻き声になってしまうからだ。辛さに涙が流れそうになるが、厚めに塗っているマスカラが流れ落ちそうで、それも必死で耐えているのだった。
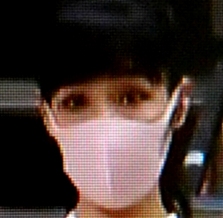
次へ 先頭へ