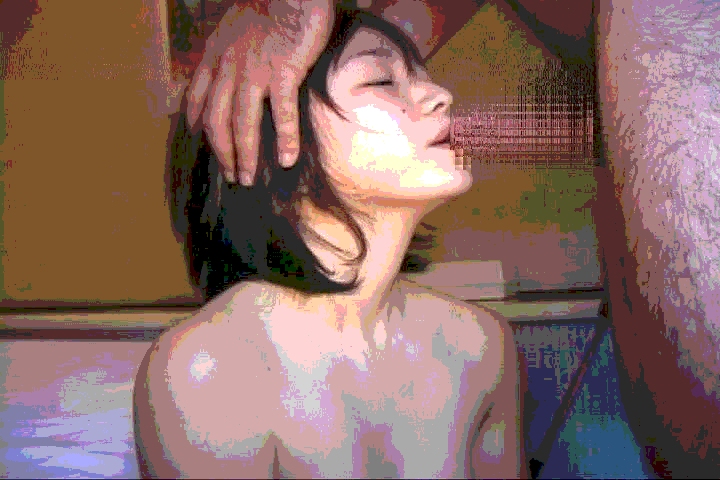
妄想小説
恥辱秘書
第五章 付き添い婦への姦計
一
芳賀は定期的に診療所へやってきていた。そしてその殆どは、巡回医や正規の看護婦が留守になる月に数回の研修日を選んでいた。その研修日になると診療所は手薄になる。大抵は受付事務をする晴江独りになってしまうのだ。
芳賀は至って健康で、何の必要もなかったのだが、血糖値が高いので定期的な血圧検査が必要だということに表向きはしていた。が、それは口実で、晴江に下半身の処理をさせるのが目的だった。晴江をトルコ嬢代わりに使っていたのだ。
晴江の股間には頑丈な貞操帯が嵌められているので、普通に性交する訳にはいかない。診療所の奥のほうでカーテンの衝立の陰で、晴江に手か口で、勃起した男根を行ってしまうまで奉仕させるのだ。芳賀は口の中にすることを好んだが、単調にならないようにたまには手で行かせるようにさせることもあった。晴江の手の中で果てた場合でも、出したスペルマを口で舐めとるように命じた。
晴江の口や手の中に放出するのにも飽きてきた頃、芳賀は晴江の貞操帯で守られた陰唇にも出してみたい誘惑にかられるようになった。正常位での性交には芳賀は興味を示さなかったが、何でも征服しないと気が済まないたちだった。
芳賀は美紀との経験から、月一度巡ってくる生理の際には貞操帯を外すことを許されている筈だと見当をつけ、いつものように晴江しか居ない日に出掛けていって、フェラチオの上に口内射精した後に、晴江に月経の巡ってくる日を教えるように言うのだった。
が、その意味をすぐに悟った晴江は、いつになくはっきりとそれを拒んだ。しかしそれは自分の愛人への貞操感からでは無かった。
晴江は時々暴力を振るう自分の恋人を懼れてはいたが、同時に愛してもいて、忠誠も尽くしていた。だからこそ、貞操帯を嵌められて不便なことがあっても、恋人が愛してくれているならばと受け入れていたのだ。
芳賀のことは弱みを握られている以上、仕方なく奉仕していた。晴江の好みの男性像とは大きく異なっていて、どんなに奉仕していても好きになれる相手ではなかった。
フェラチオの後に口内放出で口の中を穢されるのも、ただじっと堪えていた。が、フェラチオそのものにはそんなに嫌悪感を抱いてはいなかった。
ただ、生理のことについては、どうしても潔癖感を捨てきれなかった。晴江には生理の最中に性交を強いられることはどうしても我慢が出来ないことで、自分の恋人にも許していなかったことだった。
「どうしてもそれだけは嫌です。許してください。」そう言って俯いてそれ以上は一言も答えようとしない晴江だった。
しかしこの拒絶は、芳賀には許しがたい振る舞いだった。(奴隷の分際で・・・)女を蔑んでしか見ることが出来ない芳賀は、晴江に生理中の性交を拒んだことについて罰を与えることを考えたのだ。
芳賀や美紀の居るフロアの最高位にいるのは吉村という執行役員だったが、暫く前から糖尿を悪くして、定期的にインシュリン点滴をするようになっていた。最初は市内の病院に通っていたのだが、業務上多忙で難しいことも多いので、診療所の者で出来ないかと問い合わせてきたのだった。
吉村特有の我が儘で、言い出したら聞かなかった。それで、結局、看護婦の誰かがその任を仰せつかることになって、晴江が行くこともあった。
そこで芳賀は一計を案じたのだ。
次へ 先頭へ