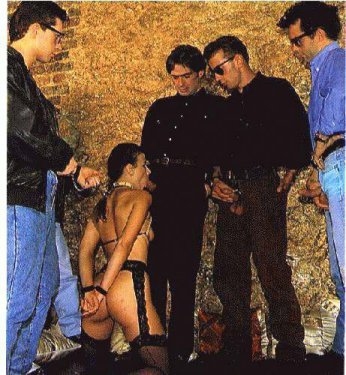
妄想小説
続・訪問者 悪夢の教団総本山
二十六
パシーン。
京子の裸の尻に鞭が炸裂する。京子は口からペニスを吐き出すようにして次の男のモノを咥える。
パシーン。
チュパッ。
パシーン。
最初のうちは男たちは鞭が手渡されるや否や、早くフェラチオして欲しさに京子の尻目掛けて鞭を振り上げていた。しかし一巡した頃からすぐには鞭を使われなくなってきた。京子は尻を打たれない代わりにペニスを咥え続けなければならなくなったのだ。
「うっ、もう出そうだ。」
前の男が果てそうになると、すかさず次の男が鞭を入れる。その阿吽の呼吸に参加者たちがだんだん慣れてきて、京子は男たちを射精直前まで咥えて奉仕しなければならなくなったのだった。
やがて一人、二人と男達の中で京子の口の中で果てるものが出始める。京子はその度に唇の端から白く濁った性液を涎のように垂らしながらフェラチオを続けていくのだった。そして最後に残った一人の口から精液が注ぎ込まれると同時に京子も白眼を剥いて失神してしまったのだった。
「目が醒めたようね。」
我に返った京子は背後から聞こえた悦子の聞き覚えのある声の振り返る。その途端、ジャラリという音がして京子の首に嵌められた首輪に鎖が付いていて壁の鉄輪に繋がれていることに気づく。京子が見回してみると自分が裸で牢獄のようなところに寝かされていたことに気づく。足元をみると、足首にも足枷が嵌められていて同じく壁の鉄輪に鎖で繋がれている。
「どうだった、献婚の儀式は? 貴方の花嫁ルーレットは男達に随分評判が良かったようじゃない。次も是非やりたいって男が大勢居るそうよ。」
京子は悪夢のような思い出に思わず頭を抱え込んでしまう。
「嫌よ。もう二度とあんな事、したくないわ。ここから私を出して。私を助けてっ。」
「残念ながらアンタには二つの選択肢しか許されてないの。ひとつは、この大伽藍の男性修道者たちの性のなぐさみ者として一生奉仕し続ける者となること。もう一つは教祖様の碑女(はしため)となって教祖様にお仕えし続けること。さ、どっちを選ぶ?」
「教祖様って、聖なるまぐわいの儀の時に私に身体を跨がせた人でしょ。私には判っていたわ。」
「そう。それじゃあ、その気持ちよさもたっぷり味わったのでしょうね。」
「もう二度と外の世界に出られないのなら、教祖様を選ぶわ。」
「そうでしょうとも。貴方もやっとまともな判断が出来るようになったのね。教祖様もそれを聞けば大変お喜びになることでしょう。今、その首輪と足枷の鎖を外してあげるわね。そしたら前の部屋まで連れていってあげるから付いていらっしゃい。」
首輪と足枷が外されると、京子は悦子から僧衣を渡される。それはちゃんと踝まで長さのある普通の修道女たちの僧衣だった。もはや京子には還俗の意志は無くなったということの象徴であるかのようだった。
元の部屋に戻された京子は教祖様の呼出しがあるまで部屋で待機するように言い渡され、悦子は教祖様に報告してくると言って京子を残して出ていってしまったのだった。
悦子が出ていってからすぐに呼出しがあるものと思っていた京子だったが、丸一日何の音沙汰もなかった。教祖様の碑女となる決意をして覚悟を固めていただけに、何の音沙汰もなしに放っておかれることが却って京子を不安にさせるのだった。
献婚の儀を受けさせられてから、不思議とペニスを跨ぐ渇望感に身体が疼きを憶えることもなくなっていた。しかし京子はそれが薬が切れてきているせいだとは知らないのだった。
その時、突然京子の部屋のドアがノックされた。
「あ、はいっ。ただいま。」
てっきり教祖様の呼出しだと思った京子はドアの前に急ぐ。しかしドアの外から入って着たのは顔の前を黒子のようなベールで覆った巫女の姿だった。
「あの、教祖様からの呼出しでしょうか?」
そう問いかける京子の言葉に返ってきたのは意外にも男の声で、しかも聞き覚えのある声なのだった。
「しっ。すぐにこれに着替えなさい。」
「そ、その声は樫山さま。」
京子が渡されたのは白い装束に赤い袴の総本山のスタッフ達が着る衣装だった。それにベールの顔隠しのついた頭巾まで付いていた。
「それを着こんだら私に付いてきなさい。ここのスタッフであるかのように堂々として、誰かに出遭ったら軽くお辞儀をするだけで言葉を発してはいけないよ。」
「わ、わかりました。」
京子には何が何だか判らなかった。が、樫山が救いに来てくれたのだけは理解出来たのだ。
樫山は慣れた様子で廊下をどんどん突き進んでいく。京子も足早にそれに従った。樫山はエレベータの扉の前まで来るとボタンを押す。
「あ、そのエレベータは・・・。」
暗証番号が無いとと言おうとしたところで扉が開く。
「さ、早く乗って。」
樫山の掛け声に京子もさっと庫内に入ると、樫山は慣れた手付きで暗証番号を打ち込むのだった。
「え、どうして・・・?」
狐につままれた気分でいると、エレベータが突然動き出した。樫山についてエレベータから出ると、もうそこは最初に京子が総本山の建物に入った入口の扉だった。
扉の外には一台の車が停めてあって、樫山は急いで助手席に乗る様に指示する。京子が乗るやいなや、車は軽くタイヤをスリップさせながら走りだしたのだった。
次へ 先頭へ