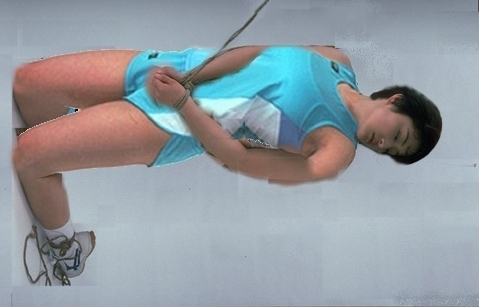
妄想小説
プール監視員
その11
バシャッ。
いきなり顔面に大量の水を浴びせられて、はっと里美は正気に返る。身動きしようにも両手首は頭の上で繋がれていてどうすることも出来ない。足を蹴り上げて防戦しようとしたが、足首にも縄が巻かれているらしく、少しも自由にならない。
「気づいたか、このじゃじゃ馬娘が。」
吐き捨てるように言ったのは、三人の男のうちで真ん中に立って空になったバケツを抱えている男だった。
「ひ、卑怯よ。あなたたち・・・。」
男たちにそんな事を言ってみても何の足しにもならないことは判っているのに、つい口に出た言葉だった。里美はまさかの事態に男たちのことを甘くみていたことをはっきり後悔していた。
「おい、その縄の端を監視台の上の手摺りに引っ掛けて思いっきり引っ張るんだ。」
男の一人が指示すると、縄が引かれて里美はずるずると身体ごと小手縛りにされたまま引き摺られていく。
「や、やめてっ。放しなさいよ。」
「黙れっ。うっせえんだよ。」
男の一人が無防備な里美の腹目掛けて足蹴にする。
「ううっ・・・。」
あまりの痛みに里美は歯を食いしばって耐える。
「おい、こいつの身体を裏返しにひっくり返すんだ。」
次なる命令に男の一人が里美の腰骨の辺りを蹴り上げるように乱暴にひっくり返そうとする。足首を繋いだ縄を持っている男もそれに加勢するので、難なく里美は俯せにさせられてしまう。俯せになった里美に再び男が逆向きに馬乗りになると里美の下半身のトランクスに手を掛ける。
「ほうれ、こうするとTバックみたいだろ。」
馬乗りになった男は里美のトランクスをパンティ毎掴むと、ぎゅっと引き絞って股布が股間に食い込むように引っ張り上げる。

「おい、ここに縄を通して結わえるんだ。おう、そうだ。おい、お前、この縄を持ってろ。」
男が結わえ付けた縄はトランクスとパンティの下を通して男の手に握られる。
「何するのよ、やめてっ。」
「おい、おれが合図したらその縄を引いてこいつのパンツを脱がしてやるんだぞ。」
「え? い、嫌っ。」
股倉に通された縄を引っ張られると聞いて、里美は慌てて足を追って脱がされるのを阻止しようとする。
「へっへっへっ。まだ引っ張らねえから安心しな。さ、おとなしく立つんだ。言う通りにしねえとアイツに言ってお前のパンツを引き降ろさせてしまうからな。」
「や、やめてっ。わ、わかったわ。」
里美は両手を小手に縛られたままおそるおそる立ち上がる。
「おい、プールの監視台をもう一台引っ張ってきてパンツに繋いだ縄も結び付けてしまえ。そっちはちゃんと監視台に繋いだか? よおし、準備は出来たな。」
里美は両手を縛った縄を一台のプール監視台の手摺りに繋がれ、それから5mほど離して置かれたもう一台の監視台の方に股倉を通した縄を結わえ付けられてしまう。弛んでいた縄を少しずつ男が引っ張るので、里美はお尻を突きだしたまま前屈みの格好を強いられる。その格好から逃れようとすれば、トランクスがパンティごと抜き取られてしまうのだ。
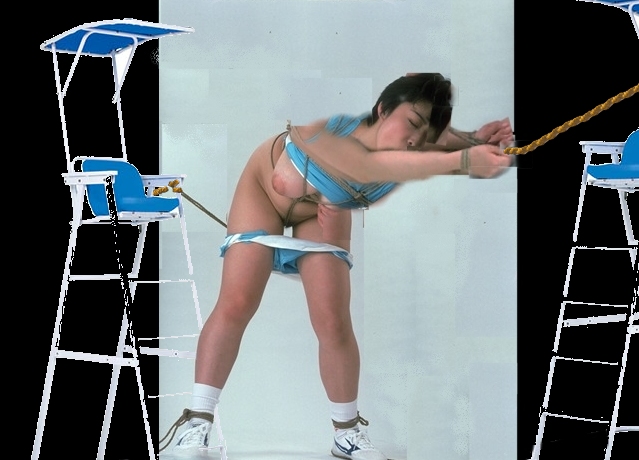
「ふふふっ。どうだい、その格好は。苦しいか? 楽になりたかったら、そこから移動していいんだぜ。ただし、そしたらパンツは脱げて下半身丸出しだがな。」
「くっ、卑怯ね。こんな格好にさせて、いったいどうしようって言うの? 」
「ゆうべはお愉しみの最中に割り込まれて、子分たちも痛い目に遭わされたっていうんで、ちょっとお仕置きをしなくちゃってね。」
「お仕置きですって? 」
「それもただのお仕置きじゃ、お前には不公平だろうって言うんでちょっとした趣向を考えたのだ。」
「趣向? どういう事? 」
「お前は剣道がいたく得意そうじゃないか。それで、お前の剣道がどれだけ通用するか試させてやろうっていう訳さ。お前が昨夜痛めつけた野郎どもがもう一度お前に挑んでリベンジしたいっていうのさ。」
「私にリベンジですって? 私に勝てるとでも思っているの。」
「さあて、それはどうかな。ただし、こいつらにはちょっとだけハンディをやらなくちゃそれも不公平ってもんさ。何せ、お前は中学時代にさんざん剣道で鍛えてきたんだろうからな。」
「ハンディ? どういう事? 」
「こいつらにはお前と試合をする前に剣道の練習をさせようって訳さ。何せまともに竹刀も振ったことが無いんでね。少し練習させてからじゃないとまともな試合にならんだろ。おい、練習の準備を始めるぞ。このプール監視台をこっちの広い場所に移動させるんだ。」
男が二人掛かりで里美が小手縛りで繋がれているプール監視台を移動させようとする。里美はそれに従って付いていかざるを得ない。しかし股間を通した縄が繋がれているほうはそのままなので、そちらの台から少しでも離れようとするとトランクスがパンティ毎引っ張られてしまう。
「ちょっと待って。これじゃ、トランクスが脱げちゃうじゃないの。」
既に里美の腰骨あたりまでが露わになろうとしている。
「じゃあ、そっちの台も少し動かしてやれ。」
そう男が命令するので監視台は再び元の5mほどの間隔に戻される。しかし腰パンぐらいに下されてしまった里美のトランクスは自分では元に直すことが出来ない。それを戻してくれと言うのも里美には屈辱だった。それにそう頼んだところでずり下がったトランクスを戻してあげてくれるとは思えなかったのだ。
「さあ、準備が出来た。お前たち、二人共。竹刀を取って来い。その間に練習用のマーキングを付けといてやるからな。」
男たち二人に命じていた男はいつのまにか赤いマジックを手にしていて、キャップを取ると小手に縛られている里美に近寄ると、里美の両方の手の甲に赤い丸印をマジックで書きこむのだった。
「何するの。そんなところにマジックで書いたりしてっ・・・。」
されながらも不安を隠せない里美だった。
「よし、お前ら。こいつの両側に立って竹刀を構えろ。お前たちも剣道の練習の素振りぐらいは知っているだろ。あれをお前たちに練習させる。ただ、普通の素振りじゃ狙った所に正確に打ち込む練習にはならないからな。お前たちにはこの赤い丸が目印だ。ここに竹刀の切先が正確に当たるように打ち込むんだぞ。」
「何ですって? 私を的にしようというの?」
「ふふふっ。そういう事だ。さ、準備はいいか。俺が号令をかけるからちゃんと打ち込むんだぞ。いいな。ようし。竹刀を構えろ。いーち。」
次へ 先頭へ