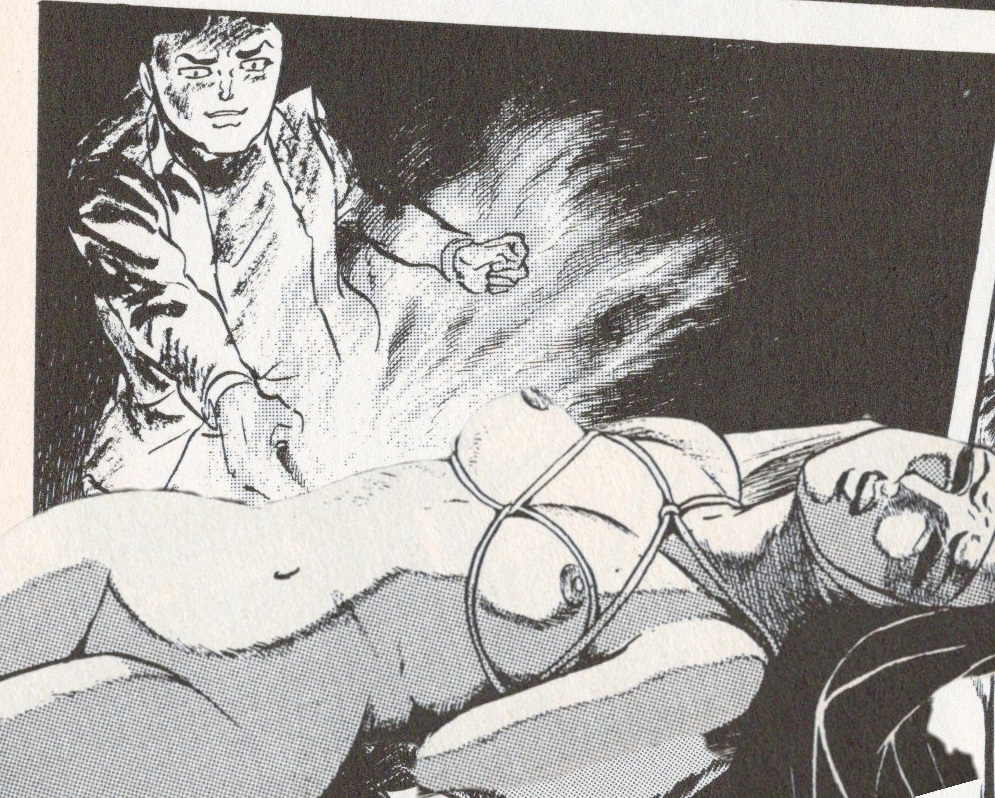
監禁妻への折檻
六十
(えっ・・・。ゆ、夢・・・?)
寝汗をびっしょり掻いたまま、倫子が何時の間にか寝落ちした転寝から目覚めたのはもう夜明け近くだった。
充電の為に机に置きっ放しにしておいた携帯に着信を知らせる点滅に気づいたのは着信から小一時間が経ってからだった。留守電の最初にひと言入っていた声だけですぐに倫子からだと気づいた琢也だった。着信記録に示されていた電話番号は知らないもので、固定電話からだった。市外局番は蓼科地方のものだったので間違いないとは思ったが、迂闊に掛け直す訳にはゆかないというのを直感した。以前、忠男と一緒に数馬と倫子の山荘を訪ねた時に、家の固定電話は解約済みで、倫子用のも個人の携帯電話は不要だから解約させたと数馬が話していたのを思い出したからだ。別荘地に山奥に公衆電話がそうそうある筈もないだろうから、何処かの家で借りたのに違いないと思ったが、事情が分からずに掛けるのは用心したほうがいいと判断したのだった。
琢也は住所を確認しようと、今年初めに届いた年賀状を探してみることにした。

それは全くの偶然だった。年賀状の束から倫子からのものを捜そうとしていて、思いがけない文字列が琢也の目に留まったのだった。
(琢也たすけて・・・?)
それは重なった年賀状の隙間から見えていた行の端だけが縦に読めてしまったものだった。
(こ、これって・・・。まさか、偶然じゃないよな。)
その時、その年に限って手書きの年賀状挨拶だったこと、宛名が倫子からだけだったことも偶々なのではない気がしてきたのだった。
(やはり、何かあるのだ・・・。)
そう思った琢也は忠男に相談して、倫子に逢いに行こうと決心したのだった。

次へ 先頭へ