
妄想小説
地に堕ちた女帝王
十六
日下は紗姫を完全に痺れさせると、さっきこっそり外しておいた手錠を取ってきて、紗姫の身体をうつ伏せに転がし、背中で両手首を交差させて手錠を嵌めた。更には真美が用意してきたSMグッズを入れてきた鞄から鎖のついた足枷を取ってきて、両足首にも嵌めてしまう。
(ま、真美、たすけて・・・。)
三度に亘るスタンガンの攻撃を受けて、身体の痺れだけではなく朦朧とする意識の中で真美に助けを求めながら、さきほど自分がしっかり縛り上げてしまった為にそれも叶わぬことに気づいた紗姫だった。
抵抗する自由を奪われながら、紗姫は目の前の日下が、実は自分を用意周到に誘き寄せたのではないかと考え始めていた。繋がれていた筈の手錠は、おそらくは最初から鍵を隠し持っていて、真美を縛るのに気を取られていた間に外されていたのだろうと想像した。スタンガンも間違いなく最初から準備されていたに違いないと紗姫は思った。
(しかし、いったい何の為に、こんな手の込んだことを・・・。)
紗姫はその時はまだ日下の卑劣な企ての全貌を掴んではいないのだった。
「さ、こっちへ来な。」
日下は紗姫の髪を乱暴に掴んで、バスケットゴールから吊り下げられた真美の元へ紗姫を引き立てていった。両手両脚の自由を奪われた紗姫は、脚を引き摺るようにして何とか従うしかなかった。
「さ、今度はお前が吊られる番だ。」
そう言うと、日下は吊られていた真美の両手、両脚首に紗姫と同じように手錠と足枷を嵌めてから、真美の身体を縛って吊るしていた縄を解く。真美が自分で逃げることが出来ないように足枷と背中の手錠を別の縄で括りつけてしまう。足枷を嵌める前に膝元から抜き取っておいた真美のショーツを無理やり真美の口を開かせて咥えこませると、上からガムテープを貼って声も出せなくしてしまう。
「お前にも後で俺の穿いていたパンツを同じように咥えさせてやるから、楽しみに待っていろよ。」
日下が歪んだ笑みを紗姫に向けているのを、紗姫は吃と睨んで返す。
真美の自由を奪ってから傍の床に転ばすと、今度は紗姫の首に犬の首輪のようなものを嵌める。鋲の打ってある幅のある革の首輪には茄子環が取り付けてあり、その輪に上から降りて来ている縄の端を結わえ付ける。紗姫は首輪ごと吊られるのを悟った。
ジャラジャラと音を立ててバスケットゴールのリングが引き上げられると、それに従って紗姫は立ち上がらざるを得ない。やっと紗姫が立っていられるだけ首輪が引き上げられると、吊り縄はそこで留められた。
さきほどと立場は全く逆転していた。裸の日下の手にはさっきまで紗姫が手にしていた調教用の鞭が握られていた。日下の股間は完全に屹立していた。紗姫をこれから懲らしめられるという期待に興奮して、ペニスを今にも爆発させんばかりに勃起させていた。
日下は裸だったが、紗姫のほうは、股下ぎりぎりの丈ではあるものの、ビザールの着衣を身にまとっている。しかし自由を奪われた格好ではいつ剥ぎ取られてもおかしくない状況ではあった。
日下はわざと紗姫をいたぶるように、自分がされたと同じことをしようとした。鞭の柄の先を後ろ手に縛られて立たされている紗姫の剥き出しの腿の内側にあて、するするとその柄の先を滑らせて、それでなくても短い紗姫の革のミニスカートをたくし上げる。
紗姫は口惜しさに唇を噛みしめ、日下のほうを睨み返す。日下の鞭の柄の先がすぐにショーツの下端に届くと、そこで柄の先を使って紗姫の無防備の恥丘をまさぐり始めた。
「くっ・・・。」
恥ずかしさよりも、口惜しさに紗姫は顔を顰めた。
「どうだい、女王様よ。さんざん鞭を使ってくれたよな。たっぷりお返しはさせて貰うぜ。へっへっへ・・・。」
身動きの取れない紗姫の身体に顔を寄せては、舌なめずりでもするかのように、見てまわっては、鞭の柄で紗姫の身体のあちこちを小突き回す。革のミニスカートの上には、同じくなめされた黒革のぴちっとした上着を身に着けている。胸元は大きく開いていて、黒い紐が交差しながら着衣を身に張り付かせている。日下はその上着の裾をいきなり掴むとぎゅっと上にたくし上げる。紗姫の白い腹が臍ごと露わになる。日下は紗姫の乳房の下端が見えだすぎりぎりまで上着をたくしあげた。鞭の柄の先が紗姫の脇腹から臍の前の締まった裸の肌の上を滑ってゆく。
それから日下は紗姫の真正面から尻のほうへ手を伸ばしてスカートを後ろでたくし上げた。スカートの下のショーツの端を探り当てると、尻タブの上を滑るようにショーツをひき下していく。黒いショーツが膝の上まで引下げられてしまうと、股間はかろうじてミニスカートの裾で蔽われているものの、お尻は丸出しになってしまう。日下はスカートがずり落ちてこないように、尻の上のところで裾をしっかりたくし込んでしまう。
その剥き出しにされた尻たぶを確認するかのように、一歩下がると、吊られた紗姫の背後に回ってゆく。
「ふん、いい尻だぜ。さっきまではSMの女王様気取りだったようだが、これからお前の性根を据え直して、きっちりとマゾ奴隷女に調教してやるから楽しみにしてな。」
不敵に笑いながら、紗姫の顎に鞭と柄を当てて、顔を上向かせる。
「紗姫、お前はこれまでさんざん俺のことを小馬鹿にし続けてきたよな。喫煙室で虫けらでも見るみたいにしか見てこなかったよな。」
「お前のことをどう思おうが私の勝手よ。こんな卑怯な手で、女に言うことを聞かせようなんて、あんたは人間の屑ね。」
紗姫の瞳は、怒りでぎらぎら燃え上がっていた。
「そんなお前が、俺のペニスでイかされたんだぜ。忘れちゃいないだろうな。お前だって所詮、メスだ。メス豚なんだよ。それをこれから思い知らさせてやる。俺に土下座して許しを請うようになるまで、たっぷりお仕置きを与えてやるぜ。」
「そんな鞭の脅しぐらいであんたになんか誰が許しを請うもんですか。」
勢いでそう言い切った紗姫ではあったが、拘束された自由にならない身では空威張りでしかなかった。
「さて、それじゃあ、そろそろ今日のスペシャルゲストを呼んで来ようかな。ふふふ。」
日下の突然の言葉に、紗姫は訝しげに日下の表情を窺がう。日下は、紗姫の視線を無視して携帯電話を取り出すと、ボタンを幾つか押して、予め用意しておいたらしいメールを送信する。すぐに返信が着信したのを見て、紗姫の顔をみながらにやりとする。
その直後に、体育館の扉がギィーと微かな音を立てて開き、ひとつの影が中に忍び込んでくるのが紗姫にも見て取れた。その暗い影は紗姫たちのところへゆっくり近づいてくるにつれ、その輪郭もはっきりしてきた。
「お、お前は、横井・・・・。」
紗姫が男の正体に気づいて挙げた言葉に、床に転がされていた真美が思わず反応した。自分の下穿きを突っ込まれて塞がれた口をもぐもぐさせて何か言おうとしているが、それは声にはならなかった。
「憶えていてくれたようだな。よかったぜ。同じお返しをするんでも、あの時のことを覚えていないんじゃ、嬉しさも半減だからな。」
紗姫は、真美を襲おうとした横井を手加減せずに懲らしめた時のことをはっきり思い出していた。あの時は、二度とそんな気を起こさないようにと、徹底的に打ちのめしたのだった。それが今、自分が手脚を括られて、何も出来ないところへ仕返しをしようとしているのだと知って、紗姫は背筋に戦慄が走るのを感じた。
日下が手にしていた調教用の鞭をゆっくり横井に手渡すのが見えた。
紗姫は、横井のこれまでにない残忍そうな含み笑いをみて、これから受けるであろう仕置きに、思わず身を震わせてしまうのだった。
「さあ、そろそろいくぜ。覚悟しな。」
横井が鞭を手にした腕が大きく振り上げられた。
ピシーィン。
「あぎゃううう・・・。」
横井の鞭の打擲は執拗だった。既に紗姫の白い尻タブは真っ赤に腫れ上がっていた。尻がミミズ腫れでいっぱいになると、今度はたくし上げられた上着の下の、臍を剥き出しにした腹が狙われた。紗姫は身を捩って苦痛に耐える。次には短いスカートから剥き出しの太腿が餌食になる。それでも、男に屈服することは自分のプライドが許さない紗姫は、唇を噛んで耐え忍んでいた。それは嘗て女暴走族の長として君臨した女帝としてのプライドだった。
「強情な奴だな。まだ許しを請わないつもりか。・・・ふん、それなら別の責め方をしてやるか。」
横井は鞭を持ち替えて、柄の先を、かろうじて股間を蔽っている革のミニスカートの裾に当てた。柄の先が持ち上げられると、紗姫の無毛の股間が露わになる。
「おやあ、お前、パイパンかあ。」
股間を剃り上げていることを初めて知った横井は素っ頓狂な声を上げる。紗姫が股間をいつも剃り上げていることを知っている日下のほうは、後ろでにやにやしている。
「股の毛を一本、一本毟り取って可愛がってやろうと思っていたんだが、毛無しじゃあしょうがねえな。」
「こいつはレズなんですよ、横井さん。そこに転がっている、真美って女に、いつもあそこを舐めさせて悦んでいるスケベ女なんですよ。」
「へえ、そいつは面白い。どうだ、ここでそいつを実演させてみようじゃないか。」
鞭の打擲に打ちひしがれて首を垂れていた紗姫だったが、二人の非情な言葉に身をびくっとさせて二人のほうを睨み返す。
「冗談じゃないわ。嫌よ、そんなこと。」
猿轡を嵌められたまま、床に転ばされている真美のほうも涙目になりながら首を横に振って、嫌がる素振りを見せる。
横井は再び紗姫のほうへ近寄ってきて、紗姫の顎を手でしゃくりあげて上向かせる。
「おめえが嫌がるかどうかは、関係ねえんだよ。ただ、股をおっぴろげていりゃあいいんだよ。よがり声を挙げるのを我慢出来るかどうか、見てやろうじゃねえか。」
「くそっ、この変態野郎っ。」
紗姫は横井の唾を吐きかけようとするが、身を咄嗟に反らした横井にかわされてしまう。その仕返しに、横井の強い平手が紗姫の無防備な顔面を襲った。
パシィーン。
「へん、いい気味だ。どっちが変態か、これからようく見てやるからな。」
日下がSMグッズを入れたバッグから、又、何やら持って近づいてきた。それは1m半ほどはありそうな鉄のパイプだった。中に鎖が通っていて、両端には足枷用の革ベルトが取り付けられている。
日下は、紗姫が蹴りで反撃に出るのを封じるように、紗姫の両足首の足枷を繋いでいる鎖を足で踏みつけて固定し、新たに持ってきた鉄パイプについたほうの足枷を片方の足首にしっかり嵌め込んでしまう。
日下の動きは用意周到で手際が良かった。首輪に掛けられて紗姫を吊っていた縄の上方に別の縄を繋ぎ留めると、その縄のもう一方の端を、新しい足枷がまだ嵌められていないほうの足首にしっかり結わえつける。紗姫は依然として首輪で吊られ、両足首を鎖を踏まれている足枷に繋がれているので、何の抵抗もしようがない。そこまで準備が整ったところで、日下は鎖を踏んでいた足を外し、元からあったほうの足枷を外す。一瞬、紗姫の脚が自由になったかに見え、すかさず蹴りを日下に与えようとした紗姫だったが、パイプの真ん中を日下に踏みつけられていて片脚は動かせない。もう片方の足にも天井から吊り下げている縄に繋がれている為に、それほど自由は利かない。日下のほうを蹴り上げようとするのだが、簡単にかわされてしまい、反対に下腹にボディブローを当てられてしまう。無防備な腹に一撃を当てられて、反撃の力を失った紗姫の背後にさっと回った日下は紗姫の首輪を外すと素早く紗姫が脚で攻撃出来る範囲外に逃れてしまう。
「く、くそう・・・。」
首が天井から吊られていた縄から自由になった代わりに、片脚には鉄パイプの足枷を繋がれ、もう片方の足は天井から降りている縄に再び繋がれてしまっているので、少し離れられてしまうと、攻撃を仕掛けることも出来ない。
口惜しそうに日下のほうを睨みつけている紗姫を尻目に、体育館の脇へ走り寄った日下は滑車の鎖をカラカラと回して、再びバスケットゴールを上へ吊り上げ始める。それに従って、紗姫は繋がれたほうの足首を少しずつ上へ引き摺り上げられてしまう。倒れてしまわないように、バランスを取りながら、片脚立ちになっているのが精一杯だった。蹴りの反撃さえ叶わない片脚立ちの状態にされてしまったところで、横井が再び近づいてきて、紗姫の腰に手を回し、顎をさすりながら、いたぶりはじめた。
「お前、レズなんだってな。お前にも自分の好きな悦びを味わわせてやる。その上で、たっぷり男にやられる悦びも教え込んでやるよ。ただし、俺様にしてくれたあの仕打ちにはたっぷりと仕返しをさせて貰ってからな。」
そう言うと腰に回した手の先を、紗姫の腰骨のところから腿の付根に沿って、下へ下へと摩りながら下ろしてゆく。すぐにその手は短いスカートの裾まで辿り着くと、今度はゆっくり裾を手繰り上げてゆく。
「くっ、・・・。」
紗姫は横井の指で陰唇を蹂躙されるのを覚悟する。
ぴちゃっ。
そのまさぐられた陰唇が、紗姫にも吃驚するような卑猥な音を立てる。
「愛しい子分の女にしゃぶられると思っただけで、もう感じてきたか。この淫乱レズ女が。」
横井は二本の指で紗姫の妖しく潤ってきている陰唇をはさむようにしてまさぐりながら、小声で揶揄するように紗姫の耳元にそう囁く。
「くっ、だ、誰が・・・。」
気丈な心を崩すまいと、強がってみせる紗姫だったが、自由にならない身のままで、恥ずかしい部分をまさぐられ、そこが意に反して濡れてしまうのを指摘されると、さすがに居ても立ってもいられない。
「こいつが邪魔なようだな。」
片膝を折るような格好で片脚立ちしている紗姫の膝小僧の上をぱんぱんに張られた黒いショーツが引き千切れんばかりになりながらぶら下がっている。その端を横井が掴むと何時の間にか用意してきたらしい鋏を尻のポケットから出して、紗姫のショーツに当てる。
シャキーン。
鋏の音が響くのと、締め付けられていた膝が開放されるのとが同時だった。それを見た日下が、バスケットゴールを引き上げる滑車チェーンを更に回してゆく。
「や、やめて・・・。」
紗姫が抗おうとどんなに力を篭めてみたところで、滑車の力に打ち勝てる筈もなかった。どんどん足首は吊り上げられていき、とうとうバランスも取れなくなって、紗姫は肩から床に倒れこむ。両手は背中で手錠を掛けられたままなので、手を付くことも出来ず、片方の足首は依然吊られたまま、大きく股を開いて片足吊りの格好になってしまう。大きく開かれた股の中心は、ショーツも奪われて、いやらしくぬめりを帯びた襞を露わにしている陰唇を丸見えにさせてしまっていた。その格好をじっくりと瞼に焼き付けるように眺めてから、横井は床に転がっているパイプを取り上げ、繋がっていないほうの足枷をもう一方の足首まで持ち上げ、パイプを開かれた紗姫の両脚へそれぞれ繋いでしまう。

両足首に嵌められたパイプの足枷のせいで、紗姫がもはや脚を閉じることも出来なくなると、日下は今度は滑車を逆に回して吊り上げられた紗姫の片脚をゆっくりと床のほうへ下ろしてゆく。攣りそうになる痛みの中で吊り下げられていた片脚が徐々に下ろされて、紗姫がほっと息をつく暇もなく、横井は天井から降りている縄を片足首から解くと、今度はパイプの真ん中へ結わえ付ける。それを待っていたかのように、日下は更に滑車を反転させる。紗姫は股を大きく開いたままの格好で、手錠を掛けられた両手を背に脚をパイプごと吊り上げられていってしまう。パイプが上にあがるにつれて、毛のない陰唇とその裏側の尻たぶが男たちの前に丸見えにされていく。
紗姫がその格好に固定されると、日下は床に転がされていた真美の元へ走りより肩を掴んで抱き起こす。
「さあ、今度はお前の出番だ。いつもの様に念入りに舐めて差し上げるんだぞ。」
日下にそう言われた真美は依然ガムテープと自分のショーツで猿轡されたまま首を振って嫌がるのだが、どんどん日下の手であられもない格好に吊られている紗姫の元へと引き立てられてゆく。
「ちょっと待て。お楽しみの前に、女帝王は最後の罰を受けて貰うことにする。その剥き出しの襞の真ん中へ、この鞭をしたたかに打ち下ろしてやる。俺も股間を嫌というまで打たれたんだ。その倍はお返ししてやらなくちゃな。」
そう言いながら、横井は歪んだ笑みを口元に浮かべ、鞭を振り上げた。
「あぎゃうううう・・・。」
引き締まった肌の尻タブを打たれるのと違って、粘膜の柔らかい肉襞を開かされた陰唇にもろに打ち据えられた鞭は、紗姫を失神させるかと思うぐらいの衝撃を股間に与えた。
不覚にも紗姫の眦から、一筋涙が垂れ落ちた。が、唇を噛みしめて堪え、降伏の言葉は吐かない紗姫だった。
「股が引き千切れてしまっては、この後が楽しめないから、今は一発だけで許してやろう。この責めは最後に取っておいてやるから覚悟しとくんだな。」
そう横井は言い捨てると、真美を抑えていた日下に顎で合図する。
日下は乱暴に真美の口からガムテープを引き剥がすと、口の中に手を突っ込んで唾液でぐしょぐしょに濡れた布切れとなったショーツを引っ張りだした。
「あぐふぐふ・・・。」
声にならない喘ぎ声を真美はあげながら、はあはあと息をする。
「さあ、愛しい愛人の股間をいつものように慰めてやんな。」
「だ、駄目よ。真美。そんなこと、しては駄目。」
男たちの目の前で、真美に股間を舐められるところを見られるのは、紗姫にとって屈辱以外の何物でもなかった。それは紗姫と真美のふたりだけの侵されてはならない奥義の世界なのだった。
肩口を掴んで真美の顔を、持ち上げられた紗姫の股間に埋め込もうとするのを真美は必死で身を反らせて抗おうとする。
「嫌です。そんなこと・・・、出来ません。」
紗姫が必死で嫌がっていることを、真美自身もやる訳にはいかなかった。
「そうか、そんなに嫌がっているなら、こいつを入れてやるぞ。」
肩を抑えている日下のほうを首を回して振り返った真美の目に映ったものは、日下の指につままれたグロテスクな器具だった。紗姫に命じられて何度もSMショップへ出入りしていた真美にはそれがなんだかすぐに悟った。肛門の中へ差し込む抽入管とそこへグリセリン液を送り込むゴムのポンプ、浣腸器だった。
「嫌、やめて・・・。そんなものを差し込むのは。」
何とか逃れようともがく真美だったが、既にショーツを奪われてしまって剥き出しになっている尻の中央を探り当てられ、注入管を挿し込まれてしまうのに、それほど時間は掛からなかった。
「いいか、真美。おとなしく言うとおりにこいつの股を嘗めないと、グリセリンをたっぷり注入されることになるんだぜ。そして我慢が出来なくなった頃合を見計らって、この女の顔を跨がせてやるぜ。そしたらどんなことになるか、わかるよな。」
日下のその悪辣な企みを知らされて、真美は従わざるを得ないのを認めた。
「言う通りしますから、そんな酷いことはしないで。」
涙ながらにそう言うと、自ら唇を尖らせて、目の前の紗姫の剥き出しの股間に顔を埋めていった。
「嫌、やめてえ・・・。真美っ、だめ、駄目よ・・・。こいつらの言うことなんか・・・聴かないでえ。」
必死の哀願も空しく、真美は狂ったように紗姫の陰唇をしゃぶりあげる。一旦始め出すと堰を切ったように真美も見境がつかなくなった。もう何も考えず、いつもの二人だけのプレイの時のように、自分等だけの世界へ没頭してしまうのだった。
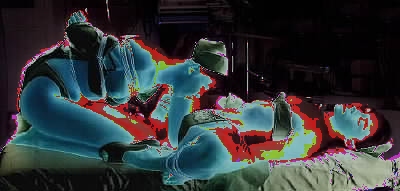
「あ・・・、だ、駄目・・・。あ・・・、ああ・・・。」
心なしか、股間を責められる紗姫の声が力なく、うわずってきていた。既に瞳の焦点が定まらなくなってきていた。
「だ、駄目っ。いっちゃう・・・。いっちゃいそうよ。」
紗姫が力なく発したその声に、真美は頭を一層激しく振りたてながら、必死で股間をむさぼり吸い捲る。
ジュポッパッ、グチュッ、ビチョッ、グチュッ・・・。
「ああ、ああ・・・・。」
二人のあさましい姿を見下ろしていた横井と日下は、二匹のメス豚どもがクライマックスを迎えそうな気配に互いに目配せして合図しあった。
日下は真美を、横井は紗姫を、肩の部分を抱いて、いきなり引き離す。
「あっ、嫌っ。離さないでっ・・・。」
首を振って嫌々をしながら泣き喚く真美の口からは涎とも愛液ともつかないべっとりしたものが垂れ落ちている。紗姫のほうも息も絶え絶えに、喘ぎながら放心しかけていた。
「お前たちのお楽しみはこれまでだ。今度は地獄の苦しみを味わってもらうぜ。」
そう言うと、日下は横井に小さな白い小壜を手渡し、自分ももう一つの小壜の蓋を取って、中からクリームをたっぷり二本の指で掬い上げ、吊られて剥き出しになっている紗姫の尻の中心の菊座にクリームを塗りこめてゆく。横井のほうも日下に倣いながら、クリームを掬い取ると、唾液でべちょべちょに濡れた紗姫の陰唇にたっぷりと塗りこんでゆく。
股間を吊り上げられた紗姫の前後の穴にたっぷりと掻痒クリームを塗りこめた後、二人の男は立ち上がった。紗姫はまだ意識が朦朧としているらしく、薬が効いてきていないようだった。しかし、直に薬が効いて、居ても立ってもいられない地獄の痒みに悶えるようになるのは日下には何度も経験済みなのだった。
「おい、こっちはどうする。」
小壜をまだ手にしている横井に、紗姫の苦しみに変わる顔を見逃すまいと紗姫のほうへまわった日下は、興味なさ気に言い放つ。
「どうでも好きにしてください。私にはそっちは興味ありませんから。」
日下のその言葉に、床に転ばされていた真美はちょっと目を攣りあげるような表情を見せた。横井は紗姫には復讐心しか湧いてこなかったが、不思議と何度か逢瀬を交わした目の前の真美にはまだ未練があるようだった。
「お前は復讐が済んだらたっぷり可愛がってやるから、もう少し向こうで待っててくれよ。」
そう言うと、横井は下半身剥き出しで括られたままの真美を抱きかかえると、体育館の隅まで連れてゆき、そこへ置いてあったマットの上へ真美の身体を横たえると、日下と紗姫のほうへ戻っていった。
既に薬は効き始めているようだった。紗姫は自由にならない身を何とかしようと身体をくねらせて身悶えし始めていた。
「何、何を塗ったの・・・。何だか変だわ。ああ、ああ、どうしよう・・・。」
「ふふふ、これをお前が使うのは始めてじゃないからな。この後、どんな気持ちになるかは判る筈だぜ。男が欲しくって堪らなくな。」
「ああ、嫌っ。痒い。あそこが痒くて堪らないっ・・・。」
目の前で腰を振るようにしながら身悶えしている紗姫を尻目に、日下は横井と最後の作戦を立てていた。
「横井さん。最後はどっちで行きますか。前の穴と後ろの穴。」
「そうさな。この高慢ちきな女の鼻をへし折ってやるのは、尻の穴を犯すほうが合ってる気がするな。その後、もう一人の人妻を犯す仕事も残ってるしな。」
「そうですか。それじゃあ、お尻のほうをお願いします。わたしは前のほうを戴かせて貰いますので。じゃあ、そろそろ準備しますか。私が抱え上げますんで、そこへ寝転んでください。」
日下はそう言うと、紗姫の両脚を開いて固定させているパイプの中に首を突っ込んで紗姫の両膝を肩で抱えて持ち上げる。その下に横井が仰向けに寝転ぶ。日下は抱えた紗姫の身体を横からそっと横井の胸元へ転がし、横井に腰をうしろから抱えさせる。用意が整うと、日下は紗姫の尻の穴の周りをわざとゆっくりと、中心には触れないように注意しながら、周りだけさすって紗姫を一層焦らさせる。
「ああ、いや、そこじゃないの。もっと奥っ。ああ、痒いっ。どうにかして。」
「それじゃあ、いくぜ。そうら。」
日下は一旦、抱えた紗姫の下半身を高く持ち上げ、両膝を大きく押し開かせるようにして、横井の屹立したペニスの中心目掛けて紗姫の尻を振り落とした。
「あぎゃあああ・・・・。」
突然の尻の痛みに顔を顰めた紗姫だったが、日下が紗姫の腿を抑えて前後に揺り動かすと、菊座に当てられたペニスの先が徐々に紗姫の尻の穴の中へ深々と押し込まれていく。その襞が擦れる刺激によって癒される肛門の痒みのせいで、紗姫は深くため息を吐いてしまう。紗姫のアヌスに深々と横井のペニスが挿し入れられたのを確認すると、今度は紗姫の陰唇の上あたりを責めはじめる。わざとクリトリスを外して恥丘の上部をまさぐる。紗姫は痒い陰唇をなんとかして貰いたくて身悶えする。
「紗姫。こっちをよく見ろ。俺様にお願いするんだ。突いてくださいと。」
日下の言われた紗姫は薄っすらと目を開いて日下を見る。口惜しさは股間の痒みに打ち勝つことは出来なかった。
「ああ、し、して。挿してっ・・・。」
紗姫の降参の表情に、してやったりとばかりの笑みを浮かべた日下は屹立した先を既にぐじゅぐじゅに濡らしている陰唇に、一気に突き貫いた。
「あううううう・・・・。」
いきなり体内にねじ込まれた二本の肉棒と、身体の前後から揺さぶられ律動されて擦れる身体内部の肉襞の快感に、紗姫は男には決して屈しないと守ってきた自分のプライドがこなごなに砕け散っていくのを、朦朧とする意識の中で、認めざるを得ない自分を感じ始めているのだった。

次へ 先頭へ