
妄想小説
覗き妻が受ける罰
第九章
最初に送りつけられた黒のタイトミニワンピースに身を包んで待つ京子の元へ携帯が掛かってきたのはぴったり11時になった瞬間だった。
「はい。わたしです。」
「今度はいいつけを守っているようだな。」
「パンツは穿いているのか?」
「・・・。え、ええ。夫の・・・、ものです。」
「どんなタイプのだ?」
「あ、あのう・・・。ブリーフです・・・。」
「どんな色だ。」
「白・・・です。」
「男物のパンツを穿いてる気分はどうだ。」
「恥ずかしいです。惨めです。」
「ノーパンのほうがいいという事か。」
「い、いえっ。ノーパンはもっと困ります。」
「もうパンツを誰かに見られたのか。」
「・・・・。あ、あの・・・。多分、宅配の人に見られた・・・かもしれないです。」
「ミニスカートの奥にブリーフを観られたんだな。よくそんな恥ずかしい事が出来るな。」
「ああ、嫌っ。言わないでください。」
「だんだん調教が出来てきているようだな。この先が愉しみだ。」
「私に何をさせようというのです・・・。」
「今にわかるさ。さ、お喋りはそのくらいにしておいて、実技にはいるぞ。ヘッドセットを付けたままで携帯を持って外に出るんだ。いつもの公園へ行け。」
「わ、わかりました。」
京子は家を出る際に玄関に鍵を掛けたほうがいいか、迷う。キーを入れるポシェットやハンドバッグを持って出るのは躊躇われた。また何か奪い取られる惧れがあった。それならまだ手ぶらのほうがいいと思ったのだ。しかし、鍵を開けっ放しの家にまた入られる恐れもあった。少し思案してバッグの中からキーホルダーだけ出して玄関を出ると施錠し、そのキーホルダーを玄関脇の植え込みの奥に隠した。辺りを窺って誰も観ていないのを確認してから門扉の外に出る。際どく短いワンピースから丸出しの生脚は、夜目にも白く浮き出て目立っている筈だ。近所の誰にも見られたくない格好だった。
京子は携帯を繋いだまま裏手の公園に向けて小走りで急いだ。
「公園に着いたか?」
「は、はい。着きました。」
「男子トイレの掃除用具室を開けて、そこに入っている黒い布袋を取ってくるんだ。そしたらそれを持って街燈から一番遠い側の樹の下まで行け。」
「わ、わかりました。」
男子トイレの傍までは人目が無い事を確認しながら、ゆっくりと近づいていき、そこから一気に男子トイレの中に飛び込んでさっと掃除用具室の扉をあけてそれらしい黒い布袋を掴むと走り出て指示された樹のもとに駆け込む。そこは公園で立った一本立っている街燈からは遠いのと、樹の葉がこんもりと茂っているので街燈から反対側に立つとかなりの暗がりだった。
「袋の中に携帯ホルダーが入っているからそれを取って首にかけろ。掛けたら持っている携帯を繋いだままホルダーの中に入れるんだ。聞こえている状態にしておけよ。」
「わ、わかりました・・・。今、掛けました。携帯も中にいれました。」
「そしたらその服はもう不要だから頭から脱ぐんだ。」
「えっ? は、裸になるのですか。」
「そうだ。」
「そんな・・・。誰が来るか判らないじゃないですか。」
「運が悪ければな。せいぜい幸運を祈ることだ。」
「そ、そんな。」
「命令を聞かないつもりか。」
「い、いえ・・・。わかりました。」
京子はもうここまで来たらなるようにしかならないと覚悟を決めて、ワンピースを脱ぎ始める。夜遅くの公園で、今は誰もいないが、そんな場所でも屋外でパンツ一枚になるのは恥ずかしかった。しかも穿いているのは男物のブリーフなのだ。しかし命令に背いた時に男に何をされるかがもっと怖かったのだ。
「ワンピースを脱ぎました。」
「そしたら服は地面に投げて袋からアイマスクと手錠を出すんだ。使い方はもう判っているよな。」
(裸でまた繋がれるのだ・・・。)
男の意図がだんだん判ってきて、怖ろしさに身体が震えてきた。
「片方の手首に手錠をしっかり掛けてからアイマスクを着けろ。そしたら両手を後ろに回して樹の幹の反対側で両手を手錠で繋ぐんだ。背中を樹の幹にくっつけるようにするんだ。そのくらいなら手探りでも出来るだろう。」
京子は一瞬迷った。しかし命令に従う他にはないのだと思い返す。片方の手首に手錠を掛ける。ずしりと重い手錠は冷たくもあった。それからアイマスクを出して頭の上から一旦首まで通し、その後目の上まで引き上げる。視界が奪われると恐怖と安堵が同時にやってくるのは、前回と同じだった。後ろに両手を回して樹の幹を探る。指が探り当てたところで、身体を背中側で幹に押し付ける。そして自由なほうの手で手錠のもう片側をたぐりよせ、手首に嵌める。
ガチャリ。
手錠が嵌り、京子の自由が奪われた瞬間を告げていた。
「手錠を嵌めました。」
「暫く待ってろ。」
男が近づいて来る気配を感じたのはそれからすぐだった。公園の傍の何処かに身を潜めていたのだろう。公園に敷き詰められた砂を踏む足音がザッ、ザッとリズミカルに響いてくる。
いきなり幹の向こう側の手首を掴まれ強く引かれる。手錠がしっかり掛かっているかを確認しているようだった。次には首に何かが巻かれる。金属ではなさそうだが、硬いものだ。分厚い革のようなものらしいと京子は見当を付ける。次には剥き出しの乳房の下に同じ様な革のベルトのようなものが巻かれ背中できつく締め上げられる。ベルトのバックルのような物が付いているらしい。その背中部分についているらしい付属のベルトが両肩から乳房のほうに下りてきて、ガチャリと嵌められる。ベルトは乳首を上へ持上げていて、更に肩からの帯が上から引っ張り上げる。革のブラジャーのようなものだが、乳首の辺りは剥き出しになっているらしかった。
胸の拘束具が取り付けられると、今度はブリーフが膝の上まで引き下ろされる。京子は何も抵抗が出来ないので、されるがままになっている。裸にされた腰に胸と同じ様なベルトが巻かれ、きつく締め上げられる。その後ベルトの後ろに付いていたやはり付属のベルトらしきものが股間に通され、ベルトの前部分でカチリと音を立てて嵌められた。京子は貞操帯のようなものを嵌められたのだと想像する。

次には樹の向こう側で手錠とは別に革の拘束具のようなものが両方の手首に巻かれ、きつく絞られてバックルのようなもので固定されたようだった。一旦手錠が外されたが、すぐに両手首に嵌められた拘束具のようなものが樹の幹から離されてから繋がれる。手錠をされていた時と同じ様に背中で両手を繋がれている。最後にジャラジャラという音が聞こえ、首に巻かれたものが引っ張られてカシャンという音と共に何かに引っ張られるようになる。鎖で繋がれたのだと京子は想像する。
「さて、準備が出来たので夜の散歩を始めるか。」
「さ、散歩って。この格好で歩くのですか。」
「そうだ。鎖で引っ張って案内してやるから曳かれる通りに歩けばいい。」
「そ、そんな・・・。」
膝の上にはまだブリーフが引っ掛かったままだ。多少は伸びるので歩けなくはないが、その姿を想像するととても無様な格好の筈だと京子は思うと泣きたくなってくる。
最初のうちは目が見えない状態で首輪に付けられた鎖で引かれるのは、両手の自由が利かないこともあって、怖いばかりだったが、次第に曳かれて前に進むのに慣れてきた。自分が足を出して踏む足音から、公園を出たことは判ったのだが、どちらの方向へ進んでいるのかは全く判らなかった。10分ほど公園を出て歩いたところで、首輪を曳かれる力が止まったのを感じ取った。
「さて、第二段階の調教の初めはここまでのつもりだったが、お前には罰を与えないといけないことになったのでここからは罰を受けるのだと思え。」
相変わらず繋いだままの携帯からヘッドセットを通じてそう話すボイスチェンジャーでゆがめられた声が聞こえてきた。身体に感じる気配で両手首を繋いだ拘束具と首輪が何らかのもので繋がれたのを感じる。するとそこに何か縄のようなものが通されたようだった。と思う間もなくそれが上の方から引っ張られるのを感じる。何かで上のほうへ吊られている感じだった。地面に付いている足が浮きそうにまでなる。かろうじて足を地面に付けていられる状態で吊り上げられてしまう。どこにも逃げることが出来なくなった状態で、股間に着けさせられたT字帯の股間部分の帯が外されたのを感じる。無毛の股間が剥き出しになっていると認識するのだが、京子にはどうすることも出来ない。その股間に男の手が伸びてきたのを感じる。

「あっ、嫌っ。何をするの?」
「罰を受けるのさ。さ、これを擦り込んでやる。」
そうボイスチェンジャーで京子に語りかけると、剥き出しにされた股間の恥部に男は何やらクリームのようなものを擦り込んでいく。それは割れ目の奥の襞にも念入りに擦り込まれていく。
「何なの? 何をしているの?」
そう問いかける京子には一切無視する形でどんどんクリームらしきものを擦り込んでいく。それは最初はカッと熱く感じたのだが、次第に違う感触に変化していくのだった。
(か、痒いっ。何っ、これは。)
次第に増してくる股間の痒みに身を捩じらせていると、一旦外されていた股間のT字帯が再びカシャリという音と共に嵌められてしまう。その内側で、京子の恥部はどんどん耐え難い痒みを帯び始めていた。
「嫌っ。何だかとても痒いの。助けてっ・・・。」
しかし、京子の必死の請いも無視されて、男は気配を消したのだった。
「ああ、もう駄目っ。痒いの。気が狂いそうだわ。お、おマンコが痒くてたまらないの。お願いなんとかして。」
そう叫びながら身を捩じらせているだけで何も出来ない京子は、聞いているのか判らない相手に向かって助けて欲しいと叫び続ける。股間の痒みに掻き毟りたい気持ちを抑えられない。しかし拘束具でしっかり両手を後ろ手に繋がれている状態では股間をどうすることも出来ない。何かに股間を当てて擦りたいと思うのだが、何処か中空から吊られているらしく、歩きだそうとすると足が浮いてしまい、その場から数歩も動く事が出来ないのだ。
痒みに悶絶しそうな状況で、どれくらいの時間放置されたのかは京子には冷静には判断出来ない状態だった。男の気配を感じた時には、京子は何を命令されてもこの痒みから逃れる為なら応じる覚悟が出来ていた。
「そこに居るの? 私が悪うございました。謝ります。ですからこの痒みから助けてください。もう気が狂ってしまいそうです。これ以上、我慢出来ません。お願いです。私を救ってください。」
京子は憐れみを請う言葉を言い続けた。
そんな京子にブーンという奇妙な音が鳴りだした。そう思う間もなく、京子の痒みを発し続けていた股間に思いもかけぬ振動が伝わってきた。何だかは判らないものの、それは京子の狂ってしまいそうな掻痒感を癒してくれたのだった。
「ああ、いいっ。いいわ。気持ちいい・・・。ああ、もっとしてって。」
その振動は掻痒感を気持ちいい快感に一瞬にして変えてしまうものだった。
「ああ、もっと・・・。もっと、押し付けてっ。」
思わず叫んでしまう京子だった。しかし、京子の思いとは裏腹に、股間に押し付けられていた振動がすっと離されてしまったのだった。
「いやっ。止めてっ。離さないで。」
再び襲ってくる股間の掻痒感に京子は身を捩じらせ始める。
「駄目っ。痒いの。お願いだから、さっきのを当てて。もう我慢出来ないの。ああ、お願い。」
「そんなに辛いか。だったら、お前の何処にバイブを当てて欲しいのかちゃんんと言ってみろ。」
「ああ、そんな・・・。お、おマンコです。おマンコにバイブを当ててください。ああ、もう我慢出来ない。ああ、バイブを・・・。バイブを当ててください。」
懇願する京子を散々焦らしてから男はバイブを京子の股間に押し当てる。
「ああ、いいっ。いいわっ。もっと・・・。もっとしてっ。」
腰をくねらせながら股間に当てられたバイブの振動に身を委ねている京子だった。
股間に与えられる愉悦に身を委ねていた京子は男が突然バイブを離したので茫然とする。
「あ、嫌っ。止めないで。バイブを当ててっ。」
そう叫んだ京子だったが、男は京子の股間を締め付けていたT字帯の股間を抑える部分を解き放ったのだった。そして次の瞬間、京子は背後からバイブを陰唇に突き立てられたのだった。
「あっ、きゃっ。いい、いいわっ。もっと、もっとして・・・。」
陰唇内に突き立てられたバイブの振動に更に京子は身体をくねらせる。
「もっと。もっと突いてっ。」
京子は既に平静心を失っていた。快楽の虜になってしまっていたのだった。しかし男の責めはそれだけでは終わらなかった。陰唇の奥に突き立てられていたバイブの切っ先が今度は後ろから京子の秘部の前面、クリトリスの裏側を責めはじめたのだ。それは今までに感じたことのない愉悦を京子に与えた。しかしそれ以上に新たな別の刺激を京子に与え始めていたのだ。
「あ、嫌っ。駄目、駄目よ。それ以上は。それ以上されたら洩らしてしまう。ああ、駄目。洩れる。洩れてしまいそうよ・・・。」
既に京子は自分でも何が起こっているのか訳が分からなくなってしまっていた。気持ち良さとは別に、してはならないことを自分がしてしまいそうなのを感じ取っていたのだ。
「ああ、駄目っ。ああ、出ちゃう。出ちゃうからっ・・・。ああ、止めてっ。ああ、どうしよう。ああ、駄目っ・・・。ああ、いくぅ。いっちゃう・・・。ああ、もう、駄目っ・・・。」
京子が自制することもままならないまま、自分の股間から何かが迸りでているのを感じ取っていた。初めての経験でそれがなんだったのかも自分で判らないでいた。
自分で抑えつけていた何かが放たれてしまった瞬間、京子は別の衝動に襲われ始めていた。掻痒感の次にきたものは、激しい尿意だったのだ。
「ああ、駄目っ。もう我慢出来ないっ。ああ、洩れちゃう。洩れちゃいそうなの・・・。」
京子が括約筋を締めようとする前に股間からは激しいゆばりが迸り出てしまっていた。それは京子の膝に中途半端にぶら下っていたブリーフをもしたたかに濡らしてしまっていた。
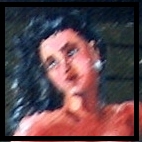
次へ 先頭へ