
妄想小説
覗き妻が受ける罰
第二十章
ピン・ポーン。
ドアのチャイムが鳴る。
(宅配便だわ。)
咄嗟に京子はそう予感する。玄関に出てみて、予感が間違っていなかった事を知る。いつもの青年だった。このところ、頻繁に宅配便を受け取るようになってきているので、すっかり顔馴染みになっている。それどころか、京子は以前についうっかりして、短いスカートのまましゃがんでしまって、下着まで覗かれてしまっているのだ。
「お届けものです。」
「あ、ありがとう・・・。待っていたの。」
受取状と一緒に、大きさの割にやけに軽い段ボールを受け取る。サインをして渡そうとすると、宅配の青年はちょっと怪訝そうな顔をする。
「あのお、不良品との交換となっていて、不良品のほうを受け取って帰らないといけないのですが・・・。」
「えっ、不良品? ・・・。」
京子は最初意味が分からなかった。しかし、段ボールに入っている筈の物の事を考えてはたと思い当たる。
(汚した下着を取り返そうとしているのだわ・・・。)
京子は返事に窮した。
「あの・・・。えーっと、まだ使っているの。返却先を教えて頂いて、私のほうから送るのでは駄目なの?」
「ああ、そういうの。駄目って規則になっているんです。」
「えっ、そうなの・・・。うーんと、どうしようかな。あ、ちょっと待って貰える?」
「ええ、いいですよ。」
京子が返品を求められている物は、将に今自分がスカートの中に穿いているものだった。それをまさか男の目の前で脱いで渡す訳にはゆかない。
京子は宅配の青年を玄関に残したまま、二階に一旦引き上げる。部屋の隅に前回、覆面マスクとマントが送り付けられた時の段ボール箱がまだ残っていた。
京子はスカートを捲って、そおっとナプキンが付いたままの汚れたペーパーショーツを脱ぎ取る。ナプキンのほうも真っ赤に汚れている。少し思案してからナプキンのほうはティッシュに包んで外し、ペーパーショーツのほうだけ厳重に包装紙で包んでからガムテープで留め、段ボールに詰めてから外側をこれも厳重にガムテープで封をする。
「お待たせしました。不良品の方を持ってきました。」
おそるおそる青年に段ボールごと渡す。
「あ、中身。確かめていいですか。」
「えっ、だ、駄目っ。駄目よ・・・。そんな事。」
「あ、いや。入っているか箱を振ってみるだけです。ほらっ。」
宅配青年は封をしたままの段ボールを上下に振って音がすることを確かめていた。京子は内心ほっとしていたが、顔には出さないように気を付けるものの心臓がばくばく音を立てているような気がした。
「じゃあ、これで。」
「あっ、待って。送り先はどこなの?」
「えっ、送り先ですか?それはそちらが注文されたところじゃないんですか?」
「あっ、ええ、そうなんだけど・・・。あ、あの・・・、以前にね。送られて来た時、大阪から届いた時と、東京から届いた時があって・・・。今回はどっちなのかなって思って・・・。」
咄嗟に吐いた嘘だった。宛先は自分の夫の名の筈だが、以前送り状には夫の単身赴任先とは全く異なる東京の住所が書かれていたのを思い出していた。
「えーっと、あ、すぐ近くですね。コンビニ預りになってます。xx町のコンビニですね。この街の業者なんですか?」
「えっ、ああ、あちこちに集配所があるみたいね。この街にもあったのかしら。」
そう言い繕った京子だったが、宅配青年が言ったコンビニは、将に男からお金を貰って生理用ナプキンを買いに行かされた店だった。
「いいですか。それじゃあ、これで。」
そう言う宅配青年を京子はただ送りだすしかなかったのだった。
そのコンビニを24時間見張り続ければ、男の正体を暴くことが出来るかもしれないと思ったが、所詮そんな事は不可能だとすぐに悟る。それに、用意周到な犯人が、自分が家に居ることを確認してからでなければコンビニに荷物を取りにいくとも思えなかったのだ。
宅配青年が去ったことを確認してから、京子は届いた段ボールを開ける。想像した通り、同じ様なペーパーショーツがたった一枚しか入っていなかったのだ。
京子は今度は迂闊に汚さないように、買ってきたばかりのナプキンを慎重に押し当ててからそれを穿くのだった。一番安いパックのそれは、粗悪品とまでは言えないが、装着感はそれほどいいものではなく、ちょっとごわごわしていて異物感が否めなかった。
常に生理ナプキンをあてたままで使っているので、ショーツの汚れは最小限に抑えられると京子は思った。何日かはそれで凌げるものの、いつまでもという訳にはいかない事も重々承知していた。だからといって、何かの手が打てる訳でもなかった。それに、男からの仕打ちがそれで全て終りと言う事にはならないだろうことは予感していた京子だった。
電話が掛かってきたのは、翌日のお昼過ぎだった。何時もの通り、ボイスチェンジャーを通したくぐもった音声だった。
「今、何を着ている?」
「な、何って・・・。貴方に渡されたミニスカートです。デニムの・・・。上はポロシャツですけど。」
「スカートの下は穿いているのか?」
「も、勿論です。昨日、送られてきたものですけど。」
「ナプキンも着けているのか?」
「そんな事まで答えなくちゃならないんですか。・・・・。着けてます。」
「そうか。・・・。送った服の中にテニスウェアみたいなのがあったろ。上下揃ったやつだ。」
「は、はい。あったと思います。白いのですよね。」
「そうだ。それに着替えろ。今、すぐにだ。」
京子は送られてきた服を思い返していた。いろんな服が取り混ぜてある中に確かに白いテニスウェアがあったのを憶えていた。勿論スカート丈は飛びっきり短い。
「着替えたら、何時ものように携帯にヘッドセットを繋いで本体はケースに入れて首から下げておくんだ。いいな。」
「わ、わかりました・・・。」
京子は嫌な予感にかられながら、寝室に行ってクローゼットから言われた服を取り出すとその場で着替える。指示はされなかったが、テニスウェアに合うように白いソックスも履くことにする。誰かに見られた時に、いかにもこれからテニスに出掛けるのだと思われるようにと考えたのだ。
携帯のところに戻ると、言われた通りヘッドセットを繋ぎ首から携帯ケースを下げてその中に繋いだ携帯を突っ込む。
「着替えたか?」
「はい、着替えました。」
「手錠は持っているな。」
「手錠・・・? え、はいっ。」
「手錠とその鍵を出してくるんだ。」
「わかりました。」
男から渡された服以外のもの一式は洋箪笥の奥に揃えてしまってある。見るのもおぞましい物ばかりだ。その中から手錠と鍵を取り出してくる。
「持ってきました。」
「パンツを脱げ。」
「えっ?」
「何度も言わすな。聞こえたろ。」
「・・・。で、でも・・・・。」
「・・・・。」
「わ、わかりました。今、脱ぎます。」
京子はナプキンの経血が服に付かないように、慎重にショーツをナプキンごと膝まで下すと、片足ずつ、ショーツから足を引き抜く。ナプキンはまだしっかりと経血が残っている。そのまま放置する訳にはゆかないので、そおっとナプキンだけ剥ぎ取ると、くるっと丸めてティッシュに包む。
「脱いだショーツはベランダの洗濯ハンガーに付けておくんだ。」
「え? そ、そんな・・・。」
ベランダには、物干し竿に空のハンガーが掛けっ放しになっている。そこへショーツを一枚だけ吊るせというのだった。誰かが注意深くみれば、ショーツ一枚だけが干してあることが判ってしまうかもしれなかった。それでも男の命令には逆らえないことは重々承知していた。
「わかりました。」
京子はショーツをつまんで部屋の中から半身だけベランダに身体を出す。視線だけ動かして、辺りをそれとなく窺ってみる。男が何処からか覗いていることは想像に難くないが、どこからみられているのかは見当もつかなかった。洗濯ハンガーは手を伸ばせば辛うじて届く場所にある。意を決してショーツを洗濯ハンガーの端の洗濯挟みに取り付ける。
「部屋に戻るんだ。」
「わかりました。」
京子は薄々、次に何を命じられるのか判ってきた。
「手錠を自分で後ろ手に嵌めるんだ。」
(やはりそうなのか・・・)
そう思ったが命令に背く訳にはゆかない。手錠の取り扱い方にはもうすっかり慣れていた。何度も夜の行進の際に自分で嵌めさせられたからだ。
ガチャリ。
非情な音が二度すると、京子はもう両手を自由に使うことが出来ない。
「鍵を手の中にしっかり握ってもう一度ベランダに出るんだ。」
「えっ? この格好でですか。外は風が吹いているのです。このスカートだと簡単に捲れてしまいます・・・。」
「だからこそ、そいつに着替えさせたんだ。つべこべ言わずに外に出ろっ。」
京子はもう一度自分が身に着けさせられたテニスウェアを観る。細かいプリーツの襞がいっぱい入っているその短いスカートは簡単に風で捲り上げられてしまいそうだった。
「ゆ、赦してっ・・・。」
涙声になりながら、言っても無駄な赦しを請う京子だったが、そんな赦しを聞いてくれる筈もなかった。
仕方なく、スカートのお尻の部分だけをしっかり抑えてベランダに一歩踏み出す。途端に風がびゅうっと吹いて来てスカートが捲れ上る。京子は必死でお尻の部分でスカートを抑えるのだが、前の部分は後ろ手錠のままでは抑えようもない。急いで身を屈めて風が収まるのを待つ。
「ベランダの端の、公園に一番近い側にいって、手摺りの前に立つんだ。」
京子はしゃがんだまま、公園側の手摺りの方をみる。手摺りは粗い桟でしかないので、公園の方に誰かいれば、どんな格好で立っているのか丸見えになる。後ろ向きに立てば、スカートが捲れた時にスカートの中を覗かれる惧れはないが、手錠を嵌めさせられているのに気づかれてしまうかもしれなかった。しかし、手錠を隠して正面を向いて立てば、風に煽られた時に下着を着けてない股間を覗かれてしまう惧れは充分にあるのだ。
「早くしろっ。」
一瞬、風が収まったところで、京子は意を決してベランダの端に近づく。そして公園には背を向けて立つほうを選んだ。手錠になるべく気づかれないように両手を出来るだけ合わせて手の平で手錠の輪を隠すようにするが、完全に見えなくなっているかは京子には確かめようもなかった。

公園に誰か居ないかはしっかり確かめなかったが、ひと気はなさそうだった。しかし、何時、誰がやってくるか判らないのだ。
また風がびゅっと吹き抜けた。京子はたまらずお尻をベランダの柵に押し付けるようにして捲れ上るのを防ごうとするが、抑えていない前は大きく翻ってしまう。公園の反対側は幸いに家が建てこんでいるし、窓も殆ど無いので誰かに見られる惧れは少なそうだった。
「も、もう赦してくださいっ。こんな格好を晒しているのは我慢出来ません。」
「ふふふ。そうか。だったら、その場で握っている手を開いて、鍵を下に落とすんだ。そしたらベランダから家の中に入るのを許してやる。」
「えっ・・・。」
京子は一瞬、躊躇ったがその窮地から逃れるには男に言われた通りにする他はないのだと悟る。
(落として、すぐに自分で拾いにいけばいいのだ。)
そう自分に言い聞かせて、ベランダの柵の間から手を外に伸ばし握った手を開いた。
「あれっ? 奥さん。何か落しましたよ。」
突然ベランダの下の方からした声に京子の背筋は凍りつく。身体を動かさないようにして首だけ振り向くと、京子の家のすぐ傍に例の作業員の男が立っているのだった。
(いつの間に、そんなところに・・・。何時から居たのだろう。)
訝しく思いながらも、京子はスカートの奥を覗かれないようにベランダの端にしゃがみこんで、後ろ手の手錠を隠しながら階下の男のほうを覗きこむ。
「これっ、鍵ですね。奥さんが落したんでしょ。今、持って行ってあげますよ。」
男はそう言うと、公園の出口のほうへ走っていく。ぐるっと廻って家の玄関のほうへ来るつもりのようだった。その時、京子は(鍵をこっちに放って)とでも言えばよかった事に気づいたが、もう後のまつりで、男の姿は見えなくなってしまっていた。
(どうやって鍵を受け取ったらいいのだろう)
そう思案しながらも京子はベランダを出て階下の玄関のほうへ急ぐ。男が居るところで後ろ手で玄関の錠を外したら手錠を嵌めさせられているのに気づかれてしまうかもしれなかった。
京子は取りあえず男がやって来る前に、玄関の施錠だけは解いておくことにして、玄関から少し離れたところに立つことにした。
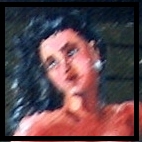
次へ 先頭へ