
妄想小説
覗き妻が受ける罰
第二十一章
ピン・ポーン。
(来てしまった・・・。)
「あ、あの・・・。鍵は開いていますので。」
男の前でわざとオレンジを袋から溢して、拾うのにスカートの中を男に覗かせた時にも玄関までは来て貰っている。男もその時の事を憶えている筈だ。だから、すぐに持っていくと答えたのだろうと京子は考えた。
ガチャリと音がして、ドアの陰から男がぬっと現れた。
「これっ、奥さんのですよね。」
男は指でつまんだ鍵を翳してみせる。しかし後ろ手錠の京子にはそれを手で受け取ることが出来ない。
「あ、それっ。そこに置いておいてくれる。」
自分から取りにいかないのを変に思われないようにするのに、どうしたらいいか京子には思いつけなかった。ただ、後ろに両手を回しているのを変に思われないためには平然と立っていることしか思いつけないのだった。
「この辺でいいですか。あれっ?」
玄関前の上り口の床に鍵を置こうとしていた男が、京子の方をみて素っ頓狂な声を突然あげたのだった。
「そ、それっ・・・。」
男が指さしているのは明らかに京子のスカートから伸びた太腿のあたりである。
「えっ?」
その指さしている辺りを覗きこんで京子は真っ青になる。太腿の内側に一筋、赤い滴が垂れていたのだ。
「きゃっ。嫌っ、見ないで。」
あまりの事に慌てて踵を返してバスルームに飛び込んだ京子だったが、男に背を向けた為に後ろ手に拘束している銀色に光る手錠をしっかり男に見られてしまっていた。

(どうしよう・・・)
とにかく、男に鍵を置いてそのまま帰ってくれるまで待つしかないと京子は思った。しかし、その時、背後に忍び寄る密かな足音を京子は聞き逃さなかった。
(まさか・・・)
京子は怖ろしさに後ろを振り向けないでいた。その京子の肩を男のがっしりとした手が両側からしっかりと掴んだ。
「手錠を掛けられていたんですね。」
耳元で囁くような声で聞こえた男の言葉に京子は答えることも出来ずに、ただ俯いているしかなかった。
「あれ・・・、手錠の鍵なんでしょ。ベランダから落したの?」
「・・・。」
京子にはそうだとも、違うのだとも答えることが出来ない。
男が肩を掴んでいる両手をぐっと自分のほうへ引き寄せる。京子はされるがままに男の方へ引き寄せられると、手錠の手が男の下半身に触れてしまう。そして、そこは既に硬直し始めているのに気づくのだった。
「僕が手錠を外してあげますよ・・・。でも、その前に。貴方にして貰いたい事があるんです。」
そう言って、更にきつく京子の身体を引き寄せる。男の股間はますます硬さを増して膨らんできている。
「だ、駄目っ。そんなこと・・・。駄目っ。駄目よっ・・・。」
そう言う間にも、男はぐいぐいと下半身を京子の手に押し付けてくる。手錠を掛けられているので、京子の方も押し付けられている所から手をどかす事が出来ない。
「さ、・・・。チャックを下してっ。」
男はやさしく、しかし強硬に京子に命じていた。京子は観念した。無言のまま、不自由な両手の指を伸ばして男のズボンのチャックを探る。男は京子の指の動きを感じて、更に勃起度をあげている。
チャックを探り当てると、ゆっくり下におろしていくとズボンの中に指を押し込む。男が履いているのは緩めのトランクスのようだった。指が前開きの窓からその中へ滑り込むと、それに反応するかのように、肉塊がブルンと飛び出てきた。
「あっ・・・。」
指に肉棒の先が触れると、すでにぬるっと濡れているのが判る。京子は不自由な手のまま男の肉棒をしっかりと掴んで握りしめる。
(ああ、大きい・・・)
京子は心の声を封じ込める。
「ああ、いい・・・。もっとしごいてっ。」
堪らず声を挙げたのは男のほうだった。
肩を掴んでいた男の手が、ゆっくり下のほうへずれていって京子の乳房をつかむ。片方の手はそのまま乳房を揉みあげるようにしながら、もう片方の手は乳房から離れて腰骨の当たりまで下され、そこからスカートの襞を捲り上げ始める。
「あっ、駄目。生理だから・・・。出来ないのよっ。」
慌ててそう言った京子だったが、もう男のペニスから手を離すことが出来ないでいた。
「俺は平気さ。その方が感じるかも・・・。」
「駄目よっ、そんな事。・・・。お願いっ。・・・。だったら口でさせて。」
京子は覚悟した。男の手を振り払うように身を翻らせると男の前にしゃがみこんだ。手は使えないので後ろ手のまま、男の屹立したモノを咥えこむ。
「うぐっ・・・。」
男は京子がペニスを口に咥えたのをみて、京子の頭を両手で掴んで更に引き寄せる。
「あぐっ・・・。ぷふっ。」
男のペニスは京子が想像したよりも太かった。息が苦しくなって一旦口に含んだペニスを吐き出す。唾を呑み込もうとするが、涎のように口元から一筋流れ出る。それを拭うことも出来ない。
京子は思いきってもう一度ペニスに唇をあてる。今度は舌を使って男のカリの部分を舐め上げ、それから再度口に含む。絞り上げるように口の筋肉をすぼめると、反応して男のモノが上に更に反り上る。
「ああ、いいっ・・・。いいよ、奥さん・・・。」
京子は夢中で男のペニスにむしゃぶりつきながら、デジャブを感じていた。夫にはフェラチオをしたことがなかった。いや、夫だけではなくフェラチオをするのは初めての経験だった。それなのになぜデジャブを感じるのかと脳裏の奥で不思議に思いながら、夢の中で何度かフェラチオをさせられるシーンを見たことを思い出した。
(あの時の感じ・・・。)
初めて実体験するフェラチオが、現実のものなのか夢のつづきなのか、京子にはもう判らなくなってきていた。
(あっ、いけない。寝てしまったんだわ・・・)
目覚めた時、一瞬自分が何処にいるのかわからなかった。身体中が痛いような、だるいような不思議な倦怠感に見舞われていた。
(あれっ・・・。私・・・、ひとり・・・なの・・・)
身体を起そうとすると、上に掛けられていたシーツがはらりと下に垂れ落ちた。服は着たままだった。しかし、下半身に手を伸ばすと肌蹴たスカートの下には何も着けていなかった。
頭がガンガンしていた。今、居るのは自分の寝室のベッドの上だとは判るのだが、どうやってここまでやってきたのかは思い出せなかった。
(えーっと確か・・・)
少しずつ記憶が蘇ってくる。バスルームで男に後ろから肩を抱きすくめられた感覚がまだ残っていた。
(そうだ。あれからあの人のズボンに手を伸ばして・・・)
京子は思い出しながらも顔を赤らめていた。
(初めてのフェラチオだったのに、初めてって気がしなかったんだ。)
京子は一生懸命、京子の口には余りあるほどのペニスを何度も吸ったりしごいたりしたのに、とうとう男は口では果てなかったのだ。
そして、身体を持ち上げられてキッチンのテーブルに俯せに寝かされて、スカートを捲られたのだった。男のモノを自分のヴァギナに後ろから挿入されて、全身に震えが起こったのを今のように思い出す。夫では感じた事のなかった快感に見舞われたのだった。男が果てる前に先にイッてしまったのは京子の方のようだった。そのまま失神してしまったのに違いなかった。だとすれば、京子の身体を二階のベッドルームまで運んだのは男に違いなかった。
(あの人は、結局イッたのだろうか。)
ベッドの上でスカートを持ち上げてみる。剃り上げたままの股間はうっすらと鮮血の痕が残っているが、精液のようなものは付着していなさそうだった。
(嗚呼、私ったら、何てことを・・・。)
股間の血糊はもう乾いてしまっていた。男が拭ってくれたのかもしれないが、それすらも覚えていないのだった。
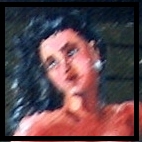
次へ 先頭へ