
妄想小説
覗き妻が受ける罰
第十一章
「奥さん。またミニスカートですね。この間まで決してミニスカートなんか穿かなかったのに、この頃はミニばっかりですね。脚を出すことに目覚めたみたいに。」
「そんなにじろじろ見ないでください。」
「いいじゃないですか。だって見せたいからそんな短いの、穿いてるんでしょ。うーん、刺激的だな。ほら、もうここ。こんなになっちゃってますよ。」
男は自分の股間を指さす。明らかにズボンの下で男のモノが膨らみだしている。
「いやっ、そんなこと・・・。わたしのせいだっていうの?」
「そりゃ、そうですよ。ほらっ、僕のムスコを慰めてくださいよ。」
「い、嫌っ。近寄らないで・・・。」
「そんなこと言わないで。ほらっ。」
男は京子に身体を擦り付けるように下半身をぴったり寄せてくる。京子は何故か魔法でも掛けられたかのように身体が動かない。京子の太腿に布を通して男の硬くなったものが押し当てられる。さっきより更に大きさも硬さも増しているようだ。
「駄目っ。押し付けないで・・。ああ、駄目だから・・・。」
「そんな事、いわないで。さ、チャックを下して、僕のムスコを自由にしてやってくださいよ。ほらっ。」
「駄目よ。そんな事。こんな真昼間に、こんな場所で。で、出来ないわ。」
「昼間だったら出来ないんですか? 真夜中だったらあんな恥ずかしい格好で出歩けるのに?」
「えっ。ま、まさか・・・。貴方、観てたの?」
「ええ、しっかりね。物凄い格好でしたよね。それに最後はお洩らしまでして。」
「嫌っ、言わないで・・・。お願い。」
「だったら、早く握るんだな。チャックをおろして。社会の窓に手を突っ込んで。ペニスを引っ張りだすんだよ。」
急に男の語気が荒くなる。それに圧倒されて、京子はおそるおそる男の股間に手を伸ばす。震える手でチャックを下すと中に指を突っ込む。途端に男のそのモノはバネで弾かれたかのようにズボンの外にそそり出てきた。
(ああ、おおきいっ・・・。す、凄いわ・・・。ああ、こんなのでされたら・・・。ああ、わたし、どうかなってしまいそう・・・。)
その時、ガクッと椅子から滑り落ちそうになって、京子は目を醒ました。京子の右の手は自分が穿いているブリーフの前開きの部分に突っ込まれていて、自分の陰唇を必死にまさぐっていることに気づいたのだった。
(ゆ、夢・・・だったのね。)
京子は自分がみていた白昼夢のはしたなさに、思わず顔を赤らめてしまったのだった。
携帯が鳴ったのは、京子が一人だけの遅い夕食を済ませてキッチンで色々思案している時だった。寛いでいるという訳にはゆかなかった。何をこれから命じられるのか不安でたまらなかったのだ。
(まさか、これで終りと言う事はないだろう)
嫌な予感はこのところお決まりになっている11時ちょっと前に現実になった。
「は、はい。京子です・・・。」
「今、何を着ている?」
携帯から帰ってきた声はいつものボイスチェンジャーを通した歪んだ低い声だった。
「あ、あの・・・。貴方から送られたジーンズのミニとポロシャツです。」
「下着は?」
「ブラジャーと・・・、それから夫のブリーフを穿いています。」
「着ているものを全部脱いでこの間の拘束具を身に着けるんだ。革のブラジャーとT字帯、そして手枷と首輪だ。アイマスクもこの間のものを持っているな。あれも頭から通して首に掛けておけ。それからこの間と同じ様に手錠も片方だけ手首に掛けておけ。」
「わ、わかりました。」
京子は急いで命じられた格好になる。
「言い付けどおりの格好になりました。」
「用意が出来たら、その格好のままベランダへ一度出るんだ。」
「そ、そんな・・・。わかりました・・・。」
京子は二階に上がってベランダに通じる掃出し窓の向こうをこっそり窺う。携帯は前回着けさせられたホルダーに入れて首から下げ、ヘッドセットを携帯に付けて指示が聞こえるようにする。掃出し窓から見える外側には人の気配は無さそうだった。京子は意を決して掃出し窓を開けてベランダに出る。目の前の公園には一本だけある街燈の近くがぼおっと見える他は、常夜灯のついている公衆トイレの男子トイレが見えるだけで、明かりの無い場所は暗くて誰かが潜んで覗いていたとしても、見えそうもない暗がりが広がっているばかりだった。ひと気はないが、男が何処からか自分のほうを覗き見ているのは間違いなかった。
「T字帯の股部分をまだ繋いでないようだな。」
京子ははっとなった。腰にベルトは巻付けたものの、股間に当てる部分は尻側でぶら下ったままだ。股間に通してベルトの前部分のバックルに嵌め込むのだとは分かっているものの、嵌めてしまえば鍵が掛かって外れなくなるような気がしたのでわざと留めないでいたのだ。
「あの・・・。これ、嵌めてしまうと外れなくなってしまうのではないでしょうか・・?」
「鍵は後で外してやるから今嵌めるんだ。」
「あ、あのう・・・。これを嵌める前におトイレに行ってきてもいいでしょうか。」
「おしっこが出そうなのなら、今その場で立ったまま出せ。」
「えっ?そ、そんな・・・。」
尿意が募っていた訳ではなかったので、すぐ出せと言われても出せそうになかった。
「どうした?今、すぐ出ないのだったら、ベルトをすぐに嵌めるんだ。そんな場所にいつまで突っ立っているつもりだ。」
「わ、わかりました。」
京子は両脚を少し広げると後ろに手を回して尻に下がっているベルトを股下から掴んで前に廻し、ベルトの前のバックル部分に差し込む。カチャリという音がして、それから幾ら引っ張っても外れそうになかった。
「準備が出来たようなので出てきて貰おうか。一番ヒールの高いハイヒールを履いてこい。」
「こ、この格好でですか。こ、困ります。お隣さんとか誰がいつ出てくるか判りません。」
「・・・・。そうだな。送った衣服の中にベアトップのミニワンピースがあっただろう。黒いやつだ。それだけなら身に着けるのを赦してやろう。」
京子は肩紐が付いてないチューブ型のニットワンピースがあったのを思い出した。丈はかなり短そうだった。
「あの、下着はつけてもいいでしょうか。」
「男物のブリーフがそんなに穿きたければ穿いてもいいぜ。」
「ああ・・・、そんな。」
京子は思わず絶句する。しかし、T字帯だけの姿よりはましかと判断する。
急いでベランダを離れると一旦室内に戻り、床に落ちていたブリーフを穿いてからベアトップのワンピースを出してきて頭から通して身に纏う。丈は想像していた通り、股下ぎりぎりまでしかなかった。なるべく裾の位置をさげようとするが、そうすると革のベルトで出来たブラジャー紛いの拘束具から丸出しの裸の乳房がでてしまう。京子は真っ直ぐ立っていればぎりぎり股間の下着が覗かないところで我慢することにする。
「手錠の鍵は家に置いて出るんだぞ。いいな。」
「わ、わかりました・・・。」
京子は目立たないように家の灯りを消したうえで、音がしないようにそっと玄関の扉を開き外に出る。家の鍵は前回と同じ様に掛けてから植込みの奥に隠す。
(誰も居ませんように・・・)そう念じながら、京子は小走りで公園に向かったのだった。
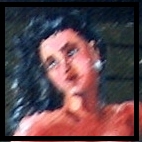
次へ 先頭へ