
妄想小説
監禁された女巡査
第十六章 仕組まれた偽装
光彦の命令は大胆なものだった。到底そんなことは出来ないと真穂は思ったが、目下のところ、言う通りにするしか由紀を救う方法はないのだった。
真穂は手錠と鎖を外されて、自由の身で外に出されることになった。と言っても、見張りの朱美と、護衛と次郎に付き添われてだった。真穂が光彦に命じられた任務は、自分の所轄である港北署へ行き、自分の拳銃を持ち出すこと。それからそのまま由紀の所轄の港南署へ行って、光彦から渡された由紀のロッカーの鍵を使って自分の拳銃と由紀の拳銃を摩り替え、由紀の拳銃を持ち帰ることだった。その間、ずっと朱美が傍にぴったりついて監視している。次郎のほうはいずれも署の外で車で待っていた。もし少しでもおかしな行動を取れば、朱美がすぐさま連絡を取る手筈になっていた。真穂はあらゆる瞬間の隙を窺がったが、とうとう誰かに合図の連絡をすることも、メモを残すことも出来ず、成功したのは、光彦に言われた通りのことを成し遂げるとこだけだった。
真穂には、光彦から言われた任務が何を意味するのか全く理解出来ていなかった。しかし人質に取られている由紀の延命を図る為には、今は言う通りにするしかないのだけは理解していた。
見張りの朱美は痴漢にあった被害者で届けを出すのに同行しているのだと署員には説明することになっていた。同じ痴漢撲滅キャンペーンの運動員であることを知っている周りの署員たちは、真穂が由紀に頼まれた荷物を取りに来たと言って、由紀のロッカーを開けるのを誰も怪しまなかったのだった。
真穂が首尾よく由紀の拳銃を持って次郎の待つ車に乗り込むと、早速手錠と目隠しのアイマスクを付けさせられ、車の床に転がされた。由紀を人質に取られている以上、何の抵抗も出来なく大人しくされるがままに従う他はないのだった。
真穂が光彦に命じられたミッションを果たしている間、由紀のほうは光彦からパソコンを経由してある映像を見せられていた。それは一人の女性を警察官が逮捕する様を写したものだった。現職の警官である由紀には、その中に出てくる婦人警官と、男性警官の制服が明らかに贋物であることを見破っていた。しかし、その二人の贋警官に応対した女性は婦人警官が警察手帳をかざすと、信用しきっているようだった。画面を食い入るように見ている由紀にもその警察手帳は本物のように見えた。
それは、真穂に告げられたのと全く同じストーリーだった。違っているのは、警察手帳は真穂の物ではなく、由紀の物を使ったと伝えられた点だけだった。由紀も拉致された際に警察手帳などはすべて奪われていた。それを使って素人女性を騙したと言われても疑いようがなかったのだ。
更には、その騙され拉致されてきた女性が自分と同じ様に壁の手枷、足枷に繋がれてマサの凌辱を受ける様をも見せられた。全ては自分のせいであると思い込まされたのだった。
その上で、真穂と同じように、自分の身分証明証の部分を一緒にコピーされて、光彦たちに服従を誓う誓約書を取らされていたのだった。
戻ってきた次郎たちの報告を聞く光彦は、一応は満足げだった。しかし、安心するのはまだ早いと考えていた。最後まで気を抜いてはならないと自分に言い聞かせる。思えばマサが迂闊なことを仕出かさないか、目を配っているのを怠ったが為に始まったことだった。
光彦は、真穂から押収した由紀の拳銃を受け取ると、それと同じ型のものを組の男を使って密かに手に入れておくように次郎に命じておくのを忘れなかった。それは、最後に真穂を解放するのに、必要なものだった。
光彦には、当初から二人の監禁中の女警察官を始末してしまうことは考えていなかった。それは将来に渡って禍根を残す最も危険なシナリオだった。しかも内田由紀、マサ、そしてマサと自分も含めて真光組との関係も知られてしまっている。真穂に関しては、どこまでの情報が警察内部に伝わっているかは不明だったが、由紀と真穂の関係から組への関連性まで辿り着かれるのは時間の問題だろうと考えていた。
始末すれば、警察の捜査が及んでくるのは必至だ。それであれば、解放する代わりに二人の口を封じるしかないのだと読みの早い光彦は考えていた。その大事な切り札の一つとなる、真穂のものではなく、由紀の持ち物である拳銃を手に入れたのは、大きな一ステップではあった。
光彦は次なるステップの調教を、二人同時進行で開始すべく、次郎とマサ、そして朱美の三人に作戦を教え込むのに、部屋へ呼び出したのだった。
最初の調教は真穂のほうから始められた。拘束された真穂の目の前から片付けられた三角木馬の代わりに、以前にも女子大生の拉致凌辱される姿を映し出した大型液晶モニタとそれに映像を写す為のパソコンが持ち込まれた。
「何をまた見せようと言うの。」
以前のことを思い出し、直ぐに光彦たちに喰ってかかるように言い放った真穂だった。
「お楽しみの映像さ。お前の同僚がどんな目に遭ったかたっぷり見せてやろう。」
そう光彦が言って映し出したのは、マサが一人勝手な行動に出て、由紀を拉致して山中に連れ出し、製材所跡で丸太に手足を縛り付けて欲情を限りを尽くした将にその時に撮影されたビデオだった。
両手を丸太に磔にされ、更にその丸太に大股開きで膝を括り付けられた由紀の姿は、見る男に欲情を誘わない筈がないあられもない姿だった。その無防備な獲物を今にも凌辱しようとして近づいているマサの股間は屹立して天を向いた太い幹が哀れな獲物の剥き出しの股間に襲いかかろうとしていた。そこに至る状況は全く知らされていない。股間の痒みに悶え苦しむ由紀の顔は、抵抗出来ずに今にも犯されようとする恐怖心からのものと真穂が勘違いしたのも無理からぬことではあった。
股間を剥き出しにして大股開きに固定された由紀の中心を被うストッキングとショーツがマサの手で引き千切られ、そのまま熱い怒張が由紀の股間に突き立てられると、真穂は自分が犯されたかのように、思わず身を震わせてしまう。
そして、マサが執拗に腰を動かしていくに連れ、由紀の顔から愉悦の気配が感じられるようになるにつれ、自分が最初にここに連れてこられた日に光彦の手で行かされてしまったことをつい思い出してしまっていた。真穂は憎き痴漢犯たちに犯されて感じてしまう無念さを由紀も味わわされたのだと思って、その口惜しさを思い量るのだった。
画面は、我慢の限界でマサの目の前で失禁を始めた由紀に向って、マサがその顔面に放尿のゆばりを浴びせ始めたところで終わった。
「ううっ、何て酷いことを。」
真穂は、自分が、秘部をまさぐられこそはしたものの、犯されることは免れていただけに、由紀の無念さが申し訳ない思いだった。しかし、それを見越した上で、光彦はその映像を真穂に態と見せたのだった。
「どうだい、お前の相棒の様子は。最後のほうは、気持ちよがっている風もあったよな。あいつだって牝だってことだな。あそこを突かれりゃ、所詮、メスの本能が燃え滾るって訳だ。」
「そんな筈、ある訳ないわ。あんた達に犯されて悦びを感じるなんて、なんて事を言うの。口惜しさと怒りで、堪らなかった筈だわ。」
真穂は由紀を庇って、必死で強がりを言ってみた。が、真穂自身にとっても、それは強がりでしかないのはよく判っていた。
「それじゃあ、お前自身で試してみるか。どこまで我慢出来るか。苦しませられたのが同僚のほうだけじゃあ、申し訳ないだろ、えっ。」
光彦は、両手の自由の利かない真穂の下半身を、嘲るかのようにそろりとスカートの上から撫で上げた。
「いやっ。」
身を捩って除けようとするが、所詮手錠と鎖で拘束された身は自由にはならない。
「あの女より我慢が出来るかどうか、これから試してやる。おい、朱美。例のものをたっぷり塗りこめてやれ。後ろの穴のほうもな。」
光彦は後ろにいる朱美のほうを振り向いて声を掛けた。それを聞いて、真穂は恐怖に背筋が寒くなるのを感じた。光彦が言う例のものとは、聞いただけですぐに何かが判った。真穂自身も、既に一度、塗られて辛い思いをしたことがあったからだ。
「や、やめてえ。あんなものを塗るなんて・・・。い、嫌よ。」
怯える真穂の表情に嗜虐心をくすぐられた朱美は、余計に嬉しそうに小さな壜を手にして真穂の傍に近寄ってきた。
「うふふふ。すぐに気持ちよくなれるわよ。ちょっと痒いけど。この痒みで堪らなくなったあそこに突き刺されると、それはもう天にも昇る気持ちよ。きっと最後は失神してしまうかもしれなくってよ。」
真穂のスカートの中に手を突っ込んで、ショーツの端に手を掛けた朱美は、恐怖に怯える真穂の蒼い顔を見ながら、嬉しそうに微笑んで見せるのだった。
「や、止めて。お願いだから。そんな酷いこと、同じ女性だったら分かる筈だわ。悶え苦しんだ上で、獣のような男達の慰みものになるなんて。」
「あら、随分と言葉が過ぎるようね。これから可愛がってもらう人たちに、獣なんて言葉使っちゃあ・・・。殿方というのよ、そういう時は。真穂のいやらしいこの疼くものを貴方様のお硬いおチxポでどうか慰めてくださいませって、殿方たちにせがんで、ちゃんというのよ。ほほほほ。」
朱美の指先がショーツの中を真穂の陰唇まで忍び込んでくると、真穂は嫌悪感に身を硬くする。が、羽交い絞めにされた手錠と鎖は、真穂に抗うことを許さなかった。
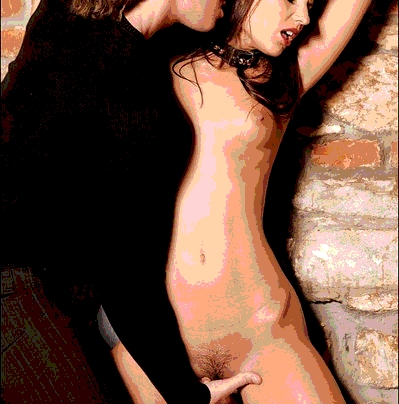
「く、くやしいっ・・・。」
淫靡なものを指で塗りこめられていくのを、唇を噛んでただ耐え忍んでいるしかないのだった。朱美の指が更に今度は後ろの尻タブに回って来た時には、更に屈辱は耐え難いものに高まった。
「なんて事をするの。貴方は人間じゃないわ。なんて卑劣な人なの・・・。」
そう言って強がる真穂だったが、朱美の指がぶすりと肉襞の奥に突き立てられてしまうと最早力を入れる元気も無くなってしまっていた。力を抜いて、もう為されるがままにじっと耐えるしかないのだと悟って、がっくり首をうな垂れた真穂だった。
身体の異変はすぐにやってきた。ふたつの穴の内部に塗り篭められた薬は、すぐに真穂の身体の中心をかあっと熱くさせた。その熱い火照りが、次第にじわりじわりと掻痒感に変わっていくのは、真穂も既に体験済みである。
真穂の身体が反応した様子を見て取ると、朱美は真穂の顔面にマスクを着けさせる。それはそれまで目隠しとして使われていたアイマスクとは違って、目の部分が開いた仮面のようなマスクだった。左右に尖った真っ赤なそのマスクは、さしずめベニスのサンマルコ広場で繰り広げられる仮面カーニバルを彷彿させた。もしくはSMの女王とでもいうような淫靡なマスクだった。そんなものを着けさせられる理由は真穂にはまだ理解出来ていない。
真穂の足首を柱に繋いでいた鎖が外されるのと、外から組の者らしい男達が一斉にホールへ雪崩れ込んでくるのはほぼ同時だった。男達も何故かそれぞれ思い思いの仮面を被っていて、手に手に、一升瓶やら、酒を酌み交わすのに使う茶碗やらを手に入ってきた。脚だけ解放された真穂は、ホールの中央に据えられていた卓袱台のような形をした低い丸テーブルの上に導かれた。その上で蹲っている真穂を囲んで、床に車座になって、酒宴を始めるらしかった。男達のうちの一人は手にビデオカメラを持っていて、少し離れたところから、男達に囲われている真穂の姿を映し撮っていた。その映像が無線を介して、階上に居るもう一人の拉致被害者、由紀の目の前のモニタに映し出されていることを、真穂はまだ知らないでいた。
次へ 先頭へ