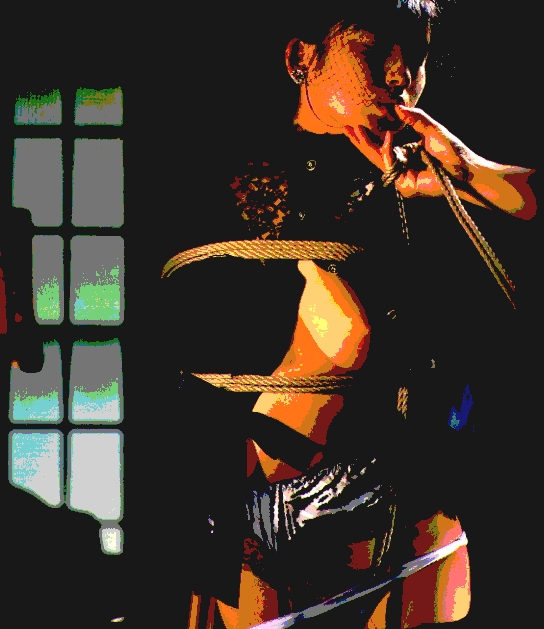
妄想小説
監禁された女巡査
第三章 最初の仕打ち
「じゃあ、俺がいいというまでは、この部屋には入って来るんじゃないぞ。」
聞いたことのない声だったので、真穂には若と呼ばれた青年が発したものだと悟る。次郎はそれには声では返事をせず、黙って奥へ通じるドアから出ていったようだった。
沈黙が流れる。真穂は神経を集中して、見えない前で気配だけでも感じ取ろうとしていた。何をされるのか不安で、身体が震えそうになるのを懸命に堪えていた。
最初に感じたのは左足の腿の前側、スカートの上を触れるかふれないかのように何かがなぞった感触だった。手の甲ではないかと真穂は思った。腿のちょうど真ん中辺りからそおっと少しだけ上へ撫で上げてきたのだ。その感触は脚の付け根まで届く前にふっとなくなった。
真穂の喉がごくりと鳴ってしまったのは、恐怖と緊張感からのものだった。
再び、今度は反対側の脚が同じように腿の中心あたりから上へ撫で上げてくる。スカートの丈はかなり短いので、裾ぎりぎりぐらいから撫で上げているようだった。
何かを押し付けるような力は入っておらず、かといって、触られているのが判らないほどではない。真穂は神経を研ぎ澄ます。
今度はかすかな感触が腿の横から腰の付近に感じられた。腰骨の付近をそおっと撫でているような感触だ。真穂は身を捩って逃れようとすると、後ろで鎖がジャラジャラと音を立てただけで、男の手から逃れるほどは身を動かせない。今度は少し力が篭められてきた。腰骨のすぐ下辺りから上へ押し上げるような感じだ。
「うっ・・・、誰っ。何をしてるのっ。」
真穂が溜まらず鋭い声を発する。しかし、それに答えはなかった。
一旦腰骨の辺りから離れた手が、今度は尻たぶのほうから、触れるかふれないかのぎりぎりの感触でそおっと撫で上げてくる。真穂は身体に電気が走ったように感じて、思わず身体を震わせてしまう。
「嫌っ・・・。」
声を出したのは、決して感じてしまったというのではないことを示したかったのかもしれないと自分自身でも思い始めていた。
するっと撫で上げると、さっと手は離れるようだった。そうされることで、今度は何処を触られるのかと、神経を集中してしまい、余計に触られることに過敏に反応してしまうのだった。あちこちに微かに触れてくるのを感じながら、(あの部分)にいずれは触れてくるのだろうことを予感する。思うだけで身体が熱くなってくるような気がしてくる。しかも熱を帯びているのが、身体の中心のあの部分に集中しているような気がして、不安になる。
何かが触れる感触がまた最初の腿の前の部分に感じられた。今度はすぐには離さず、ゆっくりと上に向って移動し始めた。だんだん脚の付け根に近づいてゆく。
真穂は思わず唾を呑み込んでしまう。
(あと少しで恥丘にまで届いてしまう・・・)と思ったとき、その感触は横へずれ、腰骨のほうへ向けて動いていった。
再び、真穂は唾を呑み込んでしまう。
今度は腰骨と身体の真ん中の間を、脚の付け根に沿って上下し始めた。腰骨の方から降りて来る度に、股にまで届くのではないかと身構えてしまう。
身体の前の方にばかり神経を集中していたので、もう一方の手が後ろからスカートの裾を持ち上げてきているのに気づかなかった。初めてそれに気づいたのは、その手の先が真穂の腿の後ろ側に触れたからだった。その冷たい感触に、真穂の身体のほうが相当火照っているのを知った。その手はゆっくりと真穂のスカートを後ろから捲り上げながら、真穂の腿の内側へと伸びていった。真穂は何故か脚を動かせないでいた。脚を閉じなければと思いながら、男の手を腿で挟み込むことにも抵抗を感じていた。真穂がじっと動けないでいると、後ろから差し込まれた手は、ゆっくりと腿の内側を撫で上げてきていた。今度は身体の裏側のほうへ神経が集中する。それを見越したかのように腰骨のほうへ当てられていた手が、真ん中の臍のほうへするすると動いていき、次第に力を少しずつ混めながらゆっくりと恥骨のほうに向って降りてきたのだった。
「ああっ・・・。」
思わず、声を発してしまってから気づいて、真穂は顔を赤らめてしまう。今にも自分の股間がまさぐられるのだと思う気持ちが、知らぬ間に真穂の気持ちを昂ぶらせてしまっていた。
(ああ、一思いに嬲ってしまって・・・。)
何時の間にかそう思い始めている自分に我ながら驚いてしまう。しかしその思いとは裏腹に前と後ろから忍び寄る手の感触は、ぎりぎりあとちょっとのところで、股の中心を外してその周りをうろうろとまさぐっている。それが真穂にはまどろしく思われ、どんどん股の中心が熱くなってしまうように感じ始めていた。
(まさか、このままされて濡れてしまうのでは・・・。)
真穂は股間の熱い火照りに、潤みを憶えてしまうのではという不安に駆られてくる。こんな自由を奪っておいて嬲るなどという理不尽なことをされながら、感じてしまうなどというあさましい姿を晒すような屈辱は何としても避けたかった。しかし、潤んでしまうという思いを一旦抱いてしまうとますます自分の股間が制御不能のままならないものになってゆくように火照りは強まっていく。
真穂の身体が微かに身悶えするように反応してきたのを見て取ったのだろう。男の後ろと前からの攻めは、微妙なリズムを持ってきた。身体の反応に合わせて力を篭めたり、抜いたりするのだ。そうされると、真穂は余計に反応を強くさせてしまうのを抑えきれなくなる。
「ああ、やめてえ・・・。ううう・・・。」
とうとう真穂は唇を噛みしめて、堪え始める。たまらなくなって、自由にならない身体のまま、真穂は大きく上半身を退け反らせる。それを観てとった男は、機を得たをばかりに両手をすかさず両腰のほうから真穂のスカートの裾をたくし上げ、生身の太腿を手のひらに包み込むように捉えると、下から掬い上げるようにする。短いスカートをつるりと捲り上げられたのを感じた。自分には見えないが、下穿きが曝け出されたのを感じ取ると、一層の恥かしさに身悶えをしてしまう。
「いやっ、いやっ・・・。」
真穂が大きく身体をくねらせ始めたのをみて、男はスカートを捲り上げた手を一旦放し、今度は手錠を掛けられている真穂の両手を片手でしっかり押さえ込み、動きを封じた。一瞬の間が流れた。そして遂に、もう片方の手が真穂の股間を捉えた。揃えて伸ばされた二本の指が下着の上からずるりと熱い火照りの中心を撫で上げたのだ。
「あああ、だ、駄目えええ・・・。」
真穂の反応は情けない叫びになっていた。下着の裏は濡れてしまっているのを真穂は確信した。男の指は下着の中心の湿り気を感じ取ると、恥骨の上に親指をしっかり据えて、二本の指を上下に割れ目の上でこすり始めた。これには真穂もたまらず、身体を横に揺さぶって逃れようとするが、男の片手が真穂の繋がれた両手をしっかり抑え込んでいるので、股間は嬲られ放題になってしまってた。
「やめてえ・・・。そこは触らないでえ・・・。」
真穂の必死の懇願も虚しく、股間を責める指の動きは次第に激しくなっていく。それに連れて、真穂は自分の抑制の効かない欲情が、疼きだしてくるのを止められないどころか、激しさを増してきているのを感じていた。
(ビチャッ、ビチャッ・・・)
遂に真穂の股間が割れ目の間から卑猥な音を立て始めた。
「い、いや・・・。」
真穂はアイマスクの下で、目蓋を潤ませながら、わが身の情けなさを呪った。
「ああ、も、もう・・・駄目っ・・・。」
真穂はがっくり首をうな垂れてしまう。その時、男の手が漸く真穂の身体を離れた。真穂は息を弾ませていた。喉が激しく渇いていて、声にならない。そんな真穂の狼狽した姿を男は見据えているかのようだった。静寂な中で、粗い真穂の息遣いだけが響いていた。
それで、男の責めは終わった訳ではなかった。自由を奪われ、何をされるのか見ることも出来ない真穂のすぐ足許に男はしゃがみこんでいたのだ。それを真穂はまだ気づいていない。男の手がこっそりと真穂のスカートの中に伸ばされていた。それを真穂が気づいたのは、お尻の下で、下着の端をしっかりと掴まれてしまった時だった。
(ぬ、脱がされる・・・。)

すぐに真穂は直感して蒼褪める。自由にならない手を伸ばして、必死で下着をスカートの上から抑えようと試みるが、お尻の上を無駄にばたばたさせるに過ぎなかった。やがて男の指に力が篭められ、真穂の股間を蔽う頼りにならない布切れは、じり、じりと下げられ始めた。腰を振るようにするが、それが余計に下着を降ろしてしまう助けになってしまうことに気づいて、今度は身を硬直させるが、すでにパンティは腰骨の下まで摺り降ろされてしまっていた。食い込んだ男の指は、ストッキングとパンティの下の生身の肌に触れている。真穂には為す術がなかった。
「く、口惜しいっ・・・。」
つい、口を出てしまった思いが、余計に真穂に自分の惨めさを感じさせてしまう。
男の手は勝ち誇ったかのように、易々と真穂の下穿きを腿の中央まで引き降ろした。ちょうど短いスカートの下から覗くぐらいの位置の筈だ。
男の手が真穂の下半身から離れ、再び真穂は静寂の中に取り残された。何もしてこないのを不審に思っていた真穂だったが、いま下ろされてしまったばかりの下着を覗き込まれているに違いないと気づいて慌てて両脚を擦り合わせるようにすぼめる。が、そうしたところで、露わにされてしまっている部分が隠せているかどうか真穂には知る由もない。それに脚をすぼめたことで、腿の上にかろうじてぶら下がっていた下着が更にずり落ちようとしていた。最早、真穂が動けば動くほど、下着はずり落ちていってしまいそうなのだった。
どれほどの間、真穂はその惨めな格好のままで、汚した下着を覗き込まれていたのか、計りしれないほどに感じていた。男の目がその剥き出しにされた下着の裏側に注がれていたのは、目の前の息遣いで痛いほどに確信していた。が、漸く男は真穂の前に立ち上がったようだった。うな垂れている真穂の顎が男の手でしゃくられ、上向かされた。アイマスクで見えないものの、男に真正面を向かされるというのは、恥かしい姿を晒し者にされた後では堪え難い屈辱だった。普段の気丈な真穂だったら、口応えだけでも相手をののしるだけの気力があった筈だった。しかし、そんな気を萎えさせてしまうだけの辱めを受けたのだった。
男は満足を尽くしたと言わんばかりの長い吐息を洩らすと、真穂の顔を放した。足音で男が少し離れたのを感じる。次に聞こえてきたのは、携帯電話を取り出したと思われる物音だった。
「次郎か。・・・。ああ、もういいだろう。但し、指一本触れちゃあ駄目だぞ。観るのは構わん。傍に寄ってじっくり覗いてやってもいいが、身体だけは触れるのは許さない。いいな。・・・、そうだ。それから、目隠しは取ってやれ。そのほうが恥かしさは増すだろうからな。・・・。そうだ。今日来る奴等にも全員それは徹底しておけよ。・・・、そうだ。今晩はずっとだ。じゃ、判ったな・・・。」
ピッという音が、携帯が切られたことを示していた。(そのほうが恥かしさが増すだろうから)という言葉と、(今晩はずっと)という言葉が真穂の耳に焼き付いていた。自分のことを差していることは疑いようもなかった。
やがて男が出て行く音がして再び静寂が戻る。しかし、真穂が安堵の息を吐く間もなく、誰かが部屋へ入って来る気配がした。誰であろうと、今の格好の真穂にとって、好ましい筈がなかった。気配で真穂の目の前にやってきたことを感じるや否や、真穂の顔からアイマスクが乱暴に引き下げられ、再び首の周りにぶら下げられる。改めて視界が戻ると、恥かしさは倍増した。男は真穂に何度も悪戯をしかけようとしたマサと呼ばれた顎鬚の男だった。嫌な中でも最も嫌な相手だ。そのマサの脂ぎった視線が膝の上に頼りなく絡まっている布切れの一点に釘付けになっているのを、真穂は見て取る。その自分の下半身の様子を敢えて覗き込む勇気が真穂にはなかった。
「へっへっへ。いい格好だぜ。・・・若にはだいぶ楽しませて貰ったみたいだな。若はあれでいて、結構テクニックがあるからな。ヒイヒイ泣いたんだろうな、きっと。・・・。今はまだ許して貰ってないが、直にお許しが出たら、俺だってお前を泣かせるぐらいのテクニックはあるんだってことを、よおく思い知らせてやるから、楽しみに待ってな。え、・・・。」
マサはそう言うと、抵抗出来ない真穂の顔の鼻をつまんで捻ろうとする。そのマサを鋭い声が後ろから諌めた。
「おい、マサ。その女に触るのはまかりならんと若に言われているのを忘れたのか。」
びくっとしてマサが首をすくめて後ろを振り返ると、次郎がドアのところに突っ立っていた。
「へっ、ち、違いますよお。ちょっと鼻をつまむ振りをして脅かしてみただけですよって。」
マサは頭を掻きながら、ホールになっている真穂が監禁されている部屋を通り抜けて、玄関の方へ出ていった。代わりに次郎のほうが真穂の傍へ寄ってきた。
「ふうん。ちょっと可愛がられただけで、随分としおれているじゃないか。マサに手錠を掛けた時の威勢はどこへ行った、あ?」
嘲るように次郎に言われると、次第に真穂には怒りがこみ上げてきた。次郎のほうをキッと睨みつける。
「貴方たち、どういうつもりなの。卑怯ものっ。」
真穂は、少女を人質に取られて屈服せざるを得なかったことを思い出した。正々堂々と戦っていたら、こんなに易々とは男等に屈することは無かった筈だと思うと、今更ながらに口惜しさが湧き起こってくるのを感じる。
真穂の目に、容易には屈しないという鋭さが戻ってきたのを、次郎は却って楽しんでいる風だった。睨みつける真穂のあられもない格好を再度上から下まで嘗めまわすようにじっくり観ると、次郎のほうもホールを抜けて玄関のほうへ出ていってしまう。
再び独りにされると、真穂は改めて部屋の様子を見回してみる。アイマスクをされていた間に何時の間にか真穂が使わされた尿瓶とティッシュ屑は片付けられていたようだった。置いてあった台座は再び部屋の隅に戻され、陶製の壺が元のように置かれていた。
部屋は洋風の洒落た造りで、ヤクザのような男達には不釣合いなものだった。上流階級のセレブな人間達が、舞踏パーティでも開きそうな雰囲気があった。没落貴族から借金の肩に取り上げた物とでもいった経緯が推測された。天井の梁や板を張った壁などは山小屋風を匂わせているが、おそらく別荘らしさを醸し出す為の演出なのだろう。大理石をあしらったマントルピースの暖炉を始め、調度品の類いは、贅を尽くしていた当時を忍ばせるものがあった。
真穂は独りで残された所在無さに、ここへ拉致されるに至るまでに出遭った人物を思い返していた。最初に痴漢として発見した男が顎鬚のマサだった。何処から見てもヤクザ風で、そんなに偉くない使いっ走りといった風情だ。犯されそうになっていた少女ははっきり顔は見ていないが、どこかで出会ったような気がするのが不思議だった。三人目は突然現れた次郎だった。こちらも見るからにヤクザだが、少し上のほうの位らしく身のこなしも俊敏だった。そしてその次郎の情婦らしき朱美、・・・。そこではたと思考が止まる。カールした髪は茶髪に染めて、いかにも娼婦のような風貌だった。しかし、どこかで観たような気がする。風俗取締りをしていた時に、どこかで掴まえたことがあるのかもしれないと真穂は思った。そして最後に現れた若という男、というよりは青年だ。色の濃いサングラスをして悪を装っているが、どうもヤクザとは違う雰囲気があった。しかしヤクザ風の次郎も、マサも一目置いていて、命令には絶対服従という感じだった。上下関係からすると、ヤクザの親分か組長の倅といったところなのだろうと、真穂は推理する。
その時、ガチャリと物音がして、また誰かが玄関にやってきたのが判る。間もなくホールの両開きドアが開いて、今度は見知らぬ頭の禿げた小男が入ってきた。小太りで、腕力だけが取り得といった感じの男だ。部屋に入るなり、食い入るように束縛された真穂の肢体に見入っている。その視線の中心はお約束のように、スカートの裾の下に露わにされた下穿きに注がれている。
小男はやがて、真穂の近くに近寄ってきた。
「ほう、こいつが例の女警官か。なるほど、なかなかいい女じゃねえか。へえ・・・。」
近くに寄って、食い入るように真穂の顔を眺めていたが、やがて腰を屈めて視線はスカートの下へ降りていく。小男は身体に触れないように気をつけながら、顔を真穂の下半身に近づけていく。くんくんと匂いを嗅いでいる様子だった。真穂は顔を横に向けて顰めながら耐えていた。
暫く鼻を近づけていたと思ったら、今度は床に這いつくばるようにして、スカートの奥を覗き込もうとする。スカート丈はかなり短いが、タイトなので、ぴったり脚を閉じてさえいれば、そう易々とはデルタゾーンまでは覗かない筈だった。しかし、身動き出来ない状態で下からスカートを覗き込まれるのは気持ちのいいものではなかった。しかも、下穿きは、膝の上まで降ろされてしまっているので、デルタゾーンは無防備なのだった。
「へっへっへえ。今夜が楽しみだなあ。」
舌嘗めずりでもするように見上げながら、再び真穂の目の前に立ち上がると、自分の股間もひとしきり揉みあげる。すでにそのモノは膨らみを帯びている様子だった。
「じゃあな。姐ちゃん。」
そう言うと、二階へ通じるらしいドアのほうへ出ていってしまった。
この小男の後も、何人ものヤクザ風の男達が出入りしては、晒し者にされている真穂の痴態を眺めては手は出さずに辱めの言葉を掛けてゆく。その建物はヤクザ達の事務所に使われているらしかった。
その日は何の会合が行なわれているのか真穂には判らなかったが、十数人の組合員らしき男達が出入りしては、通りすがりに真穂の痴態を眺めては手出しをすることなく、二階の奥へ消えていくのだった。真穂がそこに束縛されて監禁されている事情は組員にはきちんと伝えられているらしく、皆、(これが、そうか。)を真穂の風貌を関心しながら見つめ、下着を降ろされた痴態を眺めても、手出しが禁じられている為か、垂涎の眼差しを向けるだけで、身体を触ったり、スカートを捲り上げたりするようなことはなかった。しかし、それでも真穂は人が出入りする度に、屈辱を味わわない訳には行かなかった。
次へ 先頭へ