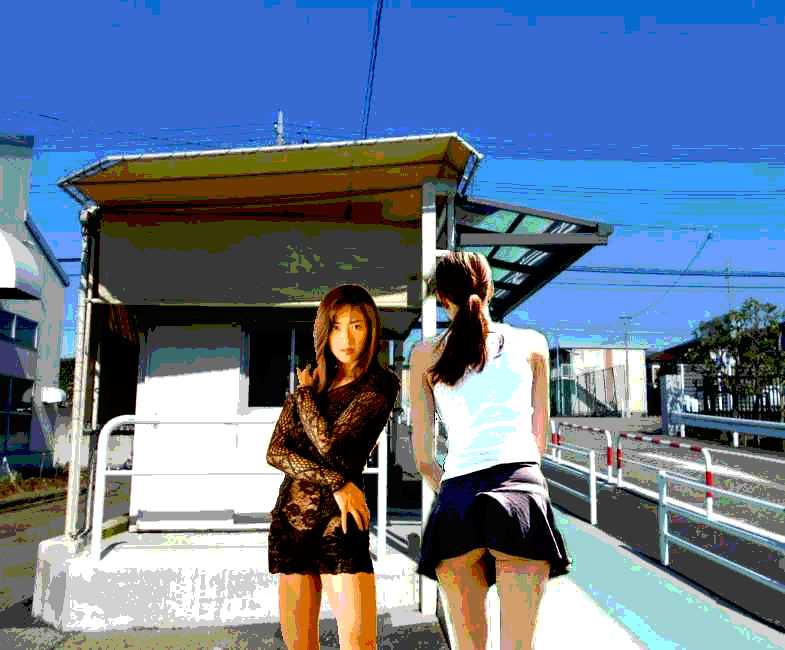
妄想小説
恥辱秘書
第十二章 忍び寄る脅迫者
十三
裕美はある程度の尿意が催してきた午前の11時頃に、とりあえず一旦出しておくことにする。バッグにトイレの清掃用具室から黙って持ってきた真新しい雑巾と替えのハンカチと濡れた体を拭うタオルをバッグに入れて、こっそり体育館へ向かった。
しかしつい急いで最短距離の表の通りを選んでしまったのだ。歩き始めて、反対側から美紀が歩いてくるのを見つけてしまった。身を隠そうと思った時には、すでに向こうもこちらを認めていて、手を振ってくる。
「あら、裕ちゃん。また逢ってしまったわね。どこ、行くの。」
何気ない言葉をさり気なくいった風を装った美紀だったが、一番痛いところを突いているのを充分知っての一言だった。芳賀に工場の建物の陰で、裕美が出てこないか、見張っているよう言われていたのだ。
「あの、・・・ちょっと。ええと、守衛さんに、守衛所に専務の荷物が届いてないか、聞きに行くところなの。」
咄嗟に出まかせの嘘をついた裕美だった。嘘と知っている美紀は、わざと裕美を困らせることにする。
「あら、守衛なんて、一本電話すれば済むことじゃないの。」
「ええ、それが、・・・何度掛けても出ないので、ちょっと外しているんじゃないかと思って・・・。それで直接確かめることにしたの。」
苦しい言い訳だった。
「だって、今日は長谷部専務、居ない日じゃなかったっけ。」
「そ、それが・・・。朝、電話があって、荷物がくるかも知れないので、着いたらすぐ報せてくれって電話があったの・・・。」
「へえ、そう。・・・ああ、そうそう。今度来た、堀田っていうやつ。知ってる。資料管理課の。前居た、助平親爺の矢作って課長、あの人が辞めたんで代わりにきたのよ。貴方もうちの若い子、北条幸江、幸っちゃんて知ってるわよね。彼女がね、・・・」
矢継ぎ早に出まかせをいう美紀だった。裕美が上の空でしか聞いていないことは充分承知の上だった。美紀の目的は、ただ裕美を焦らして引き止めることでしかない。
「あのごめんね。深堀さん。私、急いでいて。今度ゆっくり聞くから・・・。」
裕美の額の脂汗を見て、(そろそろ解放してやってもいい時期だろう。これくらい引き止めたら芳賀も許してくれるだろう)とやっと裕美を行かせることにする。ただし、最後の意地悪に、裕美が体育館ではなく、ちゃんと守衛所のほうへ向かうのを立ち止まって見届ける。
裕美は美紀を後において早足で歩き出したが、何度振り返っても美紀がみているので体育館のほうへ行くわけにいかない。仕方なく、用もない守衛所へ向かわねばならなくなってしまう。
守衛所では来る筈もない架空の荷物が来ていないかを尋ねるのだが、重役秘書ということで気を使った守衛が、「今すぐ電話で確認しますから。」と言って調べ始めたので、今度は裕美が慌てる。
「急ぎませんから、今度またで。」そう言い置くと、振り向きもせずに元来たほうへ早足で歩きはじめる。幸い、もう美紀の姿は見えなかった。前後を何度も振り返って誰も居ないのを見届けてから体育館への通用門を潜る。はやる足を音を立てないように気をつかう余裕がなくなりかけていた。一目散に真正面奥の女子トイレを目指す。
が、最後の角を曲がった裕美に無情の光景が待っていたのだ。女子トイレの扉は開けっ放しになっていて、その向こうの三つある個室には、すべて「故障。修理中」の貼り紙があったのだ。
一応、ドアノブを引っ張ってみるが、びくともしない。実は朝早く、美紀が芳賀に言われて脚立と太い針金を使って、衝立の上から内側のラッチを全てかけておいたのだった。
もう他の場所へいく余裕はないと思った裕美は、体育館のちょうど反対側にある男子トイレに向かうことにする。男に命じられて何度もいった場所で、今では勝手知ったる場所になっていた。
しかし、ここでも個室はすべて「修理中」の貼り紙でロックされていた。
次へ 先頭へ