
妄想小説
営業課長・桂木浩子 ~ 嗜虐の誘惑 (淫乱インストラクタ続編)
第十章
まさかの展開に、浩子は慌てた。さっき、管理人の口から、今は長期休暇中で寮には誰も居ないと教えられていた。しかし勝手が判らない見知らぬ建物の中で、全身素っ裸で身を隠すものはハンカチ一枚しかないのだ。それで最上階の見晴らし台まで行けという。最上階へどうやって行くのかさえも判らない。寮には誰も居ないとは言いながら、管理人は少なくとも一人は居たのだ。他に誰か従業員が居ないとも限らない。浩子はまさにパニック状態だった。ストッキングは無かったが、穿いてきたパンプスだけは残されていたので取り合えずそれを穿いた。廊下を裸足で歩かなくて済むのは助かったが、全裸には変わりない。浩子はそおっと曇りガラス戸に耳をそばだてて、外の廊下の気配を確かめる。誰も居なさそうなのを確認してからそおっと音を立てないようにゆっくりガラス戸を押し開いた。廊下はしいんと静まり返っていた。
(どっちだろう・・・)
最上階とだけしか記されていない。さっきこのシャワー室へ連れて来られた時に途中で階段の踊り場へ出たのを思い出した。あの時、更に上へ上がる階段があったことを思い出したのだ。浩子はこの建物の傍に最初に来た時のことを一生懸命思い返していた。一体、この建物は何階建だったろうか。屋上に何かあったのだったか。パニック状態のなかではとっても思い出せそうになかった。とにかくと、意を決して裸の格好のまま、走り出た。ゆっくり歩いていては、誰かに見つかるばかりだと思ったのだ。すぐに廊下の先の階段のところへ出た。上へ向う階段が続いている。浩子は辺りに誰も居ないのを確かめながら、音を立てないように壁伝いに階段を上がって行った。シャワー室のあったのは二階だった。三階まで出ると更に上へ上がれるようになっているが、そこからは広い階段ではなく、人一人がやっと通れるような細い螺旋階段になっている。
(きっとこの上が見晴らし台なのだろう。)
浩子はそう信じて先へ進むことにする。螺旋階段は窓がなくて暗いのがせめてもの救いだった。食堂から上がる螺旋階段は素通しだったが、こちらは壁に囲まれている。暗闇を進むので、とても長く遠い気がしたが、やがて上のほうに明かりが見えてきた。電灯が点いているのではなく、日の光が差し込んでいるようだった。登りきってみると、妙な部屋になっていた。八角形の全包囲窓に囲まれた小部屋で壁は腰ほどの高さまでしかない。5m四方ほどの部屋で、床は何故か絨毯が敷き詰められている。出入り口は今登ってきた螺旋階段への口と、その正反対の方向にあるアルミサッシのドアひとつだけのようだ。そのドアの傍に寄って窓から下を見ると、建物の屋上の上に突き出した塔のようになった部分であることがわかる。屋上の面からは5mほどは上にあるようだった。アルミサッシのドアの外には梯子が取り付けてあるようだった。
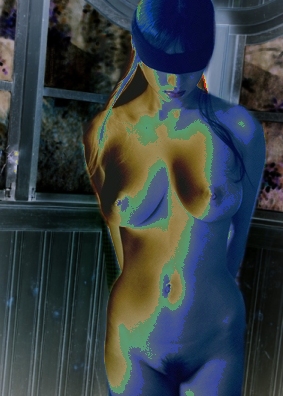
浩子は奇妙な見晴らし台らしい小部屋の中を見渡してみる。床の隅に何やら置かれているのに気づいた浩子はゆっくり傍へ近寄っていって、その物を取り上げる。拾い上げるとそれは布製のアイマスクだった。その下からは、鋼鉄製の手錠が出てきた。浩子はそれが意味するものを直感した。思わず身震いをするが、全ては身を任せて従う他はないのだった。
マスクを目に嵌めてしまう前に見晴らし台からの外の景色を眺めてみる。眼下にはところどころが畠になっているだけで、後は葦の原っぱしかない。建物のすぐ横に土手が走っていて、その更に向こうは川が蛇行しながら流れていた。浩子がトラックに乗せられてきたらしい道路はかなり遠いところにあった。そこから農道のような舗装されていない路地が一本繋がっているきりだった。あたりには人っこ一人見当たらなかった。外から覗かれる虞はとりあえずはなさそうだった。
意を決して浩子はアイマスクを目にあてた。ゴムのバンドがついていて、後頭部へ掛けるとそれで固定された。手にした手錠を手探りで開く。手錠はあのいまわしい浅川に何度も掛けさせられて悪戯されたおかげで、使い方は頭に入っていた。ギザギザの付いたレバーを開いて手首を差込み閉めるだけでラッチが掛かる。片方の手首に掛け、ちょっと思案してから両手首を背中に回して、もう片方を後ろ手にして嵌めた。文字通り何の抵抗も出来ない格好にさせられてしまった。
(自分にはこうして樫山を待つしかないのだ。)
そしてそれは自分から望んだことなのだと、浩子は自分に言い聞かせた。既に嗜虐的な思いに、下腹部は潤みを持ち始めているように思われた。浩子にはしかし、それを確かめることも、拭うことも出来ないのだ。
その時、ふと、浩子の頭にある考えがよぎった。
(これから、やって来るのがもし樫山でなかったら。もし、この見晴らし台へ導いたのが、樫山ではなかったら。自分の服を奪い、見晴らし台で目隠しを嵌めさせ手錠を掛けさせたのが、樫山ではなかったら・・・。)
浩子は自分が取り返しのつかないことをしてしまったのではないかと不安になった。自分をここまで運んでくれたダンプカーの運転手の顔を思い出す。トイレの代わりにシャワーを使えといった管理人を次に思い出す。最後に浮かんできたのは、今朝方駅で擦れ違い様、跨線橋の下でミニスカートの奥を覗き、尻を撫でた三人の男たちの顔だった。
(誰が来てもおかしくないのではないだろうか。自分は誰か見知らぬ男たちの餌食になり、性の慰みものにされるかもしれないのだ。)
そう思った途端に、浩子は身体の芯を何か熱いものが走るのを感じ、それが子宮から恥骨の裏側へ届いて、何かを滴らせたように感じた。
(ああっ・・・。)
その時、カタンと小さな音がしたような気がした。浩子は裸の身体を凍りつかせる。足音はさせないのだが、誰かが確実に擦り寄ってくるのが気配で感じられた。浩子は背中の手錠を嵌めた手を強く握リしめる。が、それは何の役にたつ訳ではないのだ。
いきなり二の腕の部分をきつく掴まれ背中側から抱き寄せられた。後ろ手の浩子の手が服の上から男の身体を感じる。そしてその中心に硬い物が屹立していることに気づいてしまった。掴まれた二の腕の反対側から手が伸びてきて、剥き出しの乳房を鷲掴みにされた。浩子は思わず力が抜けて膝ががっくり曲がりそうになるが、男の手が強く乳房を下から支えるように抑えているので、浩子は男の腕にぶら下がるような格好になってしまう。二の腕を掴んでいた手が離れて、脇腹からだんだん下へ降りてくる。腰骨のところまで達すると、滑るように身体の中心までするりと降りてきた。
(ああっ、駄目っ・・・)
浩子は声にならない悲鳴を挙げた。
男の手のひらが恥骨の上をしっかり包み込み、指二本がその下の割れ目に沿って添えられる。ぬるっとした感触が、自分の分泌している体液のせいなのだとは思いたくなかった。が、優しく曲げられた指先が、その割れ目に忍び込んできて、びちゃっという音を立てると、もう疑いようも無かった。しっぽり濡れそぼった割れ目を探り当てると、二本の指先はその潤みを搾り出すかのようにまさぐってきた。
びちゃっ、びちゃっ、じゅるっ、浩子の恥かしさに耳を蔽いたくなる思いとは裏腹に、自分の器官とは思えないような部分が卑猥な音を立て続ける。浩子は緩く開いた膝を徐々に外側へと開いていかざるを得なかった。親指がクリトリスの上の恥骨から覆い被さるように揉みしだき、割れ目から中へ食い込むように曲げられた二本の指がその下の襞を挟み込むようにしてなぞり上げる。あまりの快感に、浩子はもう緊張の糸を切らしてしまう。途端に腿の内側を滴が垂れていくのが感じられた。しかし、浩子にはもうそれを抑えることも出来ない。男の指が浩子の襞を挟み込んだまま、上下に激しく股間全体をまさぐり始めた。手の動きはどんどん速く激しくなっていくのに連れて、浩子は下半身の中心から何やら汁を撒き散らし始めているのを頭の遠くのほうで感じていた。
「いや、駄目っ。は、恥かしい・・・。」
今度は声に出して叫んでしまっていた。
男は浩子が感じきってしまったのを見て取ると、そおっと浩子を抱き下ろし、絨毯の上に膝と肩をつかせて這わせ後ろに回りこんだ。男が両側から浩子の裸の尻をしっかり抑え込むの感じると、浩子は来るものを期待して待った。突然、熱い肉棒が浩子の体内を貫いた。
「あうううっ・・・。」
指の責めで高められた興奮は、後ろからの挿入で一気に天へと昇るようだった。
「いいっ・・・。ヒィーっ」
最早、言葉にはならなかった。男の激しい突きに、アイマスクの下の眼は白目を剥いていた。
次へ 先頭へ