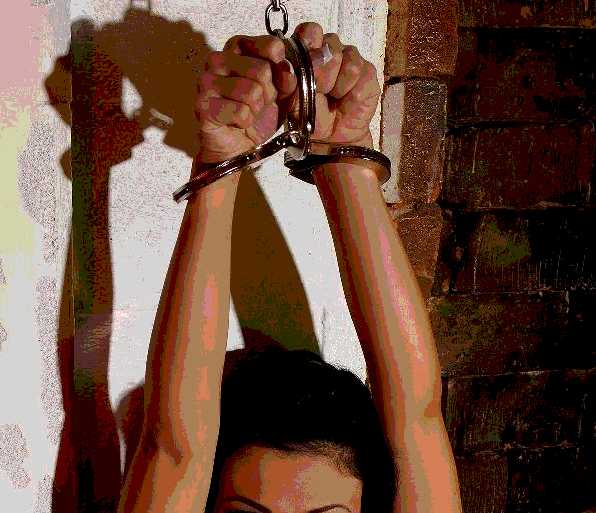
早季子先生
十一
二人はいっこうに現われる様子がなかった。しかし、もう手錠を掛けてしまったので、自由を奪われたまま逃げることも出来ない。こんな格好を見られたら、何と言い訳すればいいのだろう。
必死だった為忘れていた股間の疼きも再度襲ってきていた。しかも、それによって次第に尿意も覚えはじめていた。最悪の事態である。便器の真上にいるくせに貞操帯を着けたままでは漏らしてしまうことも出来ない。
早季子は身体を捻って悶えるしか手はなかった。
早季子は襲ってくる痒みと尿意に歯を食いしばって我慢していたが、彼等はなかなか現われなかった。随分と長い時間と感じられた後にやっと、誰かが近づいてくる足音がした。しかし、それが一人の足音と気付いて、早季子は不安になった。
ピタン、ピタンというサンダルのだらしない歩き方の足音は特徴があった。早季子の同学年の小林教諭であった。いつも中年のいやらしい目つきで早季子のミニスカートから伸びている脚を舐めるように見ている男である。あんな男にこんな格好のところを見つかったら、何をされるか分かったものではない。早季子は音を立てないように身を固くする。じっとして息を潜めていると、股の疼きは一層つのった。
足音はゆっくり近づいてきて、早季子の居る個室の真正面で止まった。早季子は心臓が飛びだしそうに感じた。いまにもトイレの取っ手が回って扉が開かれそうだった。
しかし、次に聞こえたのはズボンのチャックを下ろす音と、ジャーっという放尿の音であった。
早季子は、ただひたすら終わるのを待っていた。やっと終わって出ていこうとした音が聞こえたと思ったら、二人組がやってくる足音がする。
(まずい。)瞬間、早季子はそう思った。
案の上、小林教諭の怒鳴る声が聞こえた。
「何だ、おまえら。こんな時間に授業も出ないで何してる。」
「い、いや。そのう・・・。腹の具合がおかしくて・・・。」
「おまえら、二人共がか。ああん。」
「それが、昨日、二人して食べたアイスクリームが当たったみたいで。今朝から二人共どうも下痢気味で・・・。先生、ちょっと失礼。」
隣の個室の開く音がする。続いて更に向こうで個室の戸を開ける音。
「早く授業に戻るんだぞ、いいな。」
そして又ピタン、ピタンというだらしないサンダルの音がして次第に遠のいていった。
誰もいなくなったのを確かめるようにそっと隣の戸がゆっくり開く音がして、早季子の入っている個室の扉が開け放たれた。
「お、お願いっ。もう、我慢が出来ないの。は、はやくして。」
「早季子先生。何を我慢出来ないのさ。正直に言ってごらんよ。」
「い、いじわるしないで。もう、も・・・、漏れそうなの・・・。お願い。」
「何が漏れそうなのか、言ったら外してやるよ。先生。」
「・・・。そんなにわたしを辱めたいのね・・・。お、おしっこがしたいの。」
「ふふふ。男子生徒の前でおしっこしたいなんて、恥ずかしくないのかい。」
しかし、健二はやっと早季子の腰に手を掛けた。小さな鍵を取り出すと、貞操帯の上前をカチャリと外した。股の締め付けられていたのが、やっと自由になった。しかし、貞操帯だけ外すと、健二は再び起き上がって、ただにやにやしながら早季子を眺めている。
「て、手錠をはずして。お、お願い。早くっ。」
「いやだよ。このまま、漏らすんだ。俺たちの見ている前で。」
この残酷な言葉を聞いた途端、もう我慢出来ないのを早季子は悟った。白いパンティはまだ穿いたままである。その中心部分がみるみる染まってくると、早季子の太腿を熱いものが滴り流れた。一度漏れ出すと、もう止められなかった。
健二は早季子が漏らしだしたのを見届けると、やっとさきこの手錠を片手だけ外した。早季子は屈辱感に堪え切れず、股間を抑えるとその場にしゃがみ込んでしまった。まだ片方の手首には手錠が掛かったままである。
「先生、いい眺めだったよ。また、今度も楽しませてもらうからね。」
そう言い捨てて、早季子の足元の床に溜まっている漏らしたばかりの小水の中に手錠の鍵をポチャリと落すと、健二と勝の二人は意気洋々と出て行ってしまったのだった。
ふたりの早季子への苛めはだんだん陰湿になっていくようだった。それだけに一層早季子の屈辱感も大きかった。
自分で流した小水のなかに手を伸ばさなければならなかった。濡れた鍵を拾い上げるとトイレットペーパーで拭った。手錠を外し、スカートを直した。それから濡れたストッキングとパンティを脱いだ。捨てていく訳にもいかなかった。誰も居ないことを確かめてから手洗いのところへ行って、水で洗った。再び穿くわけにもいかず、小さくまるめると手の中に隠し持った。スカートの下は素足にノーパンの格好だが、外からは分からない筈だった。しかし、スカートの裾は少し濡れてしまっている。早季子はしかし何気なく振る舞うしかなかった。早季子は小走りに男子トイレを出て職員室に向うのだった。
完
TOP頁へ戻る