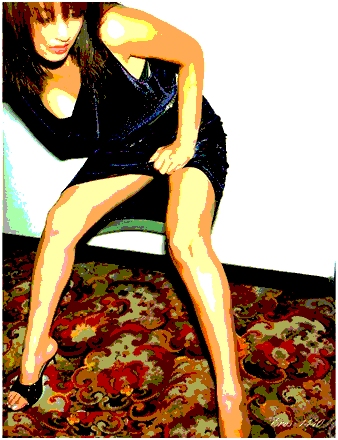
妄想小説
恥辱秘書
第一章 嵌められた女秘書
二
美紀は芳賀のほうが吃驚するくらいに慌てていた。くるりと踵を返すように芳賀のほうを振り返ると手にしていたものを後ろ手に背中に隠したようだった。
「ちょっと、コーヒーを混ぜる用のスプーンを探しに来たんだけど。」
咄嗟に芳賀は嘘をついた。
「あっ、ちょっと待ってください。ええっと、・・・。」
美紀は何食わぬ顔をして、芳賀に背を向けないようにして横ずさりに食器戸棚に近づいていった。その時、芳賀は美紀が背の後ろの手で、ゴミ箱にさっき手にしていたものをポトリと落としたのを見逃さなかった。
「はい、これ。」
美紀は戸棚の抽斗からスプーンを取り出すと、芳賀に差し出した。
「あ、ありがと。・・そうだ、忘れていた。深堀さん、重役が探していたよ。」
「え、そうですか。じゃあ、すぐ。」
慌てて出て行く美紀を芳賀は見届けてから、ゴミ箱に手を伸ばした。
芳賀が思ったとおり、それはティッシュを丸めたものだった。つまんですぐにそれが湿っているのが分かる。鼻に近づけると、女そのものという匂いがつんと鼻をつく。
芳賀は実は給湯室の戸棚のことは精通していて、何処に何があるかはよく知っている。フリーザーパックのビニルの袋を戸棚の隅から取り出すと、丁寧にその濡れたティッシュを入れると、ぴっちり封をして、背広の内ポケットに仕舞う。
芳賀は重役が席に居ないのを知っていて、美紀に(重役が探している)という話をしたのだった。美紀が重役の席に行き、居ないのを不審に思って再び給湯室に戻ってくる。気になっていたゴミ箱をちらりと見るが、先ほどの後に、誰かがお茶殻を捨てたらしく、べっとり濡れたお茶殻が一面に散らばっていて、自分が捨てたものがその下に紛れているかどうかはもう確認しようもなかった。まさか、それが芳賀の手にしっかり握られているとは思いもしなかったのだった。
次へ 先頭へ