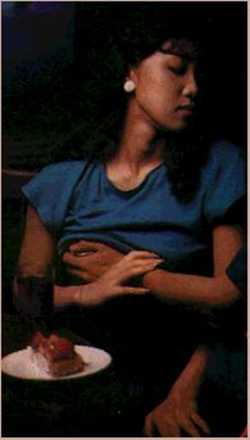
妄想小説
恥辱秘書
第十四章 再びの仕組まれた接待
五
美紀に代わって沢村のすぐ横に座らせられた裕美の膝に、沢村は遠慮なく手を乗せてくる。裕美は括約筋をぐっと締めていることに神経が集中していて、普段なら気になって仕方がない男の手の動きに気もそぞろになっている。それをいいことに、沢村に扮した原は裕美の膝を弄ぶようにさすってくる。
沢村の他愛もない話や、面白くもない冗談に、空返事で愛想を返しながら、裕美はトイレに立ったものか、そのまま気づかれないように紙おむつに洩らしてしまったものか、そればかりを考えていた。
芳賀のほうは、沢村との会話には極力加わらないようにして、黙って呑んでいる。分をわきまえた振る舞いのようにも見えるようにしながら、実際は募り来る尿意に裕美が限界を迎える瞬間を見逃すまいと注視していたのである。
間合いを計って席に戻ってきた美紀は、裕美の限界に間に合った。しかし、傍目にもじもじと身体を動かしている様子に、それは近いことを見てとる。美紀は芳賀に目配せで合図すると、今度は芳賀が立ち上がる。
「じゃあ、私はこれで会社に戻りますので。君たち、後は頼んだよ。内村君、最後は君が沢村様をタクシーでお送りして。いいね。」
「あ、はい。かしこまりました。」
長谷部専務の代行として連れてこられた裕美は、(専務代行なのだから当然なのかしら)と露も疑わない。しかし、目下のところ、帰りのことは裕美の頭には入ってこない。
芳賀が部屋を去ってすぐに今度は沢村が立ち上がる。
「じゃあ、俺もちょっとトイレに行って来ようかな。」
(あの、私も、・・・。)という声が裕美の喉まで出掛かった時に、今度は美紀も立ち上がった。
「あの、私もちょっとおトイレに。何だか、今日は呑みすぎたのか、おトイレが近くなっちゃって。ごめんね。裕ちゃん、ひとりにして。ちょっと待っててね。」
美紀は、沢村の手を取るようにして二人で部屋を出る。まさか、(私も)とは言えない裕美だった。少なくとも、どちらかが帰ってくるまでは席を立てない。その時には、もうかなりぎりぎりのところまで来ていた。二人のうちどちらかが帰ってきてからでは、もう間に合わないかもしれないと思った。
裕美は、一人になった今のうちに紙おむつに洩らしてしまうことを決心した。目をつぶって、いつも秘書室の部屋でやらされているように、ゆっくり括約筋を緩める。
(ああっ・・・)
じわっと生温かいものが股間に広がる。随分我慢をしていたせいか、どんどん流れ出てゆく。我慢していたものを放出できる安堵に、うっとりと恍惚感さえ感じる裕美だった。
が、異変に気づいたのはそのすぐ後だった。
次へ 先頭へ