
妄想小説
プール当番
第六章 屋外放置
圭子がそこへ磔にされた頃は、もうかなり夜もふけていたし、日曜の夜ということもあって、外を出歩く人影も、通り過ぎる車もなかったようだった。強烈なスポットライトが真っ暗闇の中で圭子の姿態を浮かび上がらせていたので、もしそこを通りかかれば、その格好に息を呑んだかもしれない。
幸いなことか、誰にもその辱められた姿を見られなかった代わりに、助け出されることもなく、朝を迎えた。
さすがに圭子も疲れてうとうと寝てしまったらしかった。だんだん明るくなってゆく夜明けのなかでふと目を覚ましたのは、募ってくる尿意からだった。
しかもその頃には、圭子の尿意も限界に近かった。正門前の公衆電話のところから手錠を掛けられて目隠しをされたまま曳かれている時から、かすかに尿意はあったのだが、冷たい外の風をまともに受けて立たされているうちに、それは我慢の出来ないものになっていた。
両脚を擦り合わせるようにして堪えていたが、募り来る尿意に、外の風は更にそれを煽ってくる。
(男は朝になったら)と言っていた。男が来るまで堪え切れるか自信はなかった。
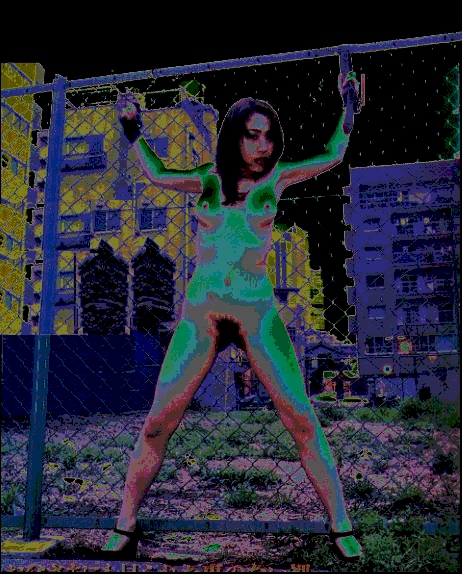
やっと男がやってきたのは、あたりがもうかなり明るくなってからだった。圭子を照らして浮き上がらせていたスポットライトの照明は何時の間にか消されていた。男がやってきたのは足音で分かった。
「もう許して。お願いだから、解いて。」
男は圭子のすぐ後ろに来ているらしく、耳元から囁くような声がした。
「だいぶ辛そうだな。夜更けに一晩中、こんな格好で風に当ってたらどうなってくるか、誰にだって分かるもんな。 . . . したいんだろ。」
圭子は見透かされて、顔が赤くなる。
「先生がお漏らししちゃ、恥ずかしいものな。もう暫く我慢するんだぜ。」
男はフェンス越しに手を伸ばして、圭子に昨夜のようにまず目隠しをする。視界を奪ってから、作業を始めるところは周到だった。
最初に、圭子の右手の自由を奪っている手錠の金網側を外し、背中の真中に新たにそれを掛ける。次に左手の端も同じ様に金網側を外して、それを今度は後ろ手になっている圭子の右手に掛ける。そして首輪を金網に繋いでいる鎖を外して後ろ手の圭子の手錠の真中に繋ぐ。これで、ここに連れてこられたのと同じ状態になった。この間、ずっと逃れる隙を窺っていた圭子だったが、一瞬たりともそのチャンスはなかった。目隠しをされているので、派手に動くことも出来ない。それは、そのまま階下への転落を意味していたからだ。
首輪に手を掛けられて、そのまま曳かれていった。フェンスの扉の中へ入ったようだった。安心感にへなへなとその場へしゃがみこんでしまう。そんな圭子を再び首輪を曳いて、圭子は立ちあがらされた。
圭子の頬に何か冷たいものが押し当てられた。
「何だか分かるかい。手錠の鍵さ。これを今からある場所に貼り付ける。」
圭子は下半身が探られるのを感じた。股ぐらを探られ、そこに何かが押し当てられた。ガムテープを貼られているのが、感触で分かる。
「用務員の鮫津に頼んで外して貰うんだな。」
圭子の目隠しが乱暴に外された。目の前に視界が急に開けたと思った瞬間目の前で閃光が走る。この間と同じ手口だった。目の前でフラッシュが焚かれた為、暫く残光で何も見えない。その間に男が走り去って行く足音が聞える。圭子は後ろ手で、しかもその手錠は背中で首輪に繋がれている為に何も出来ない。ただ、ひたすら目の前のちかちかが治まるのを待つしかなかった。その間にも非情に尿意はどんどん募ってきていた。
やっと目が見えるようになってきて、まだ開いているバルコニーのドアを目指した。もうあと何分我慢出来るか分からない。パンティはまだ膝まで下ろされていたままだが、自分の手で直すことも出来ない。そのままの不自由な格好で、圭子は用務員室を目指した。
用務員の鮫津にはもう既に恥ずかしい格好を目撃されてしまっている。こんなことは出来るだけ広げたくなかった。パンティがずり落ちないようにしながらも必死の速度で圭子は用務員室へ急いだ。この時間なら鮫津はもう来ている筈だった。
階段を駆け下り、職員室の廊下を走り抜け、まだ誰もいない校舎を抜けて裏手にある用務員室へ圭子は急ぐ。
目の前に漸く、用務員室が見えてくる。圭子は股間の筋肉をきつく締める。(あと少しの我慢だわ。)そう自分自身に言い聞かせる。
「鮫津さん、居るの。中へ入れて。は、早く。」
手が自由でないので、首で扉を叩くように押す。
暫くして開いた扉を、待ち切れないかのように中へ飛びこむ圭子だった。鮫津が不審そうに圭子の格好を見下ろしていた。
圭子は両手を背中に回して、短いスカートの膝までパンティを下ろしている。
襲ってくれと言わんばかりの格好である。
しかし、圭子には余裕がなかった。が、その次の言葉は、さすがに言いよどんだ。
「あ、あの、 . . . 」
次の言葉は下を向いてしか言えなかった。
「スカートの下に、手錠の鍵が貼り付けられているの。それを取って、外してください。」
鮫津にはこの前の威しが効いているのか、どうしようか躊躇っているようだった。しかし、圭子にはもうゆっくりしている余裕がない。恥ずかしさに火を吹くような感じを覚えながら、圭子は脚を開いたまま腰が屈めた。スカートがばっくり割れて、その下が鮫津の目の前に露わになる。
「この下に手錠の鍵が貼り付けてあるの。それを剥がして、手錠を外して。お願い、早くっ。」
自分の弱い立場を悟られないように、しかし懇願するように圭子は頼んだ。
鮫津が恐るおそる近寄ってきて、股間に手を伸ばしてきた。鮫津の喉元がまたごくんと鳴っている。鮫津の手が自分の股間に触れるときにはさすがに横に顔をそらした圭子だった。
ベリベリという音と一緒に、陰毛を抜かれる痛みに堪えながらも圭子は鮫津に身を任せているしかなかった。(ほうっ、)という声で、鮫津が鍵を見つけたことがわかった。
その鮫津がそれを手に圭子の背中に廻った。圭子は早く手錠を外してほしさに括られた両手首を鮫津に向かって差し出す。が、鮫津の手はそこで凍りついたように止まってしまった。

次へ 先頭へ